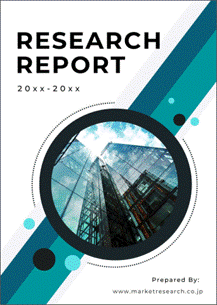 | • レポートコード:BONA5JA-0339 • 出版社/出版日:Bonafide Research / 2024年5月 • レポート形態:英文、PDF、67ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:生命科学 |
| Single User(1名様閲覧用、印刷不可) | ¥333,000 (USD2,250) | ▷ お問い合わせ |
| Corporate License(閲覧人数無制限、印刷可) | ¥703,000 (USD4,750) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要
精神衛生上の問題の頻度が高まり、精神衛生に対する文化的見解が流動的になるにつれ、日本の精神衛生市場は、近年、国内のより大きなヘルスケアシステムにおける重要な戦場となっています。このダイナミックな分野は、文化的信念から経済的現実まで、多数の要素に影響されるため、興味深く多様な研究対象となっています。最先端の技術と豊かな文化遺産で知られる日本では、現在、深刻な精神衛生上の危機が起こっています。歴史的に粘り強さと禁欲主義で知られてきたこの国では、現在、活発な活動と理解の広がりに後押しされ、メンタルヘルスに対する考え方がパラダイムシフトを迎えています。 政府機関、テクノロジー企業、製薬会社、医療サービス提供者など、幅広いプレイヤーが日本のメンタルヘルス市場に参入しています。 高齢化社会、都市化の進展、職場の力学の変化などが、このエコシステムを推進し、メンタルヘルスサービスやソリューションへの需要を高める要因となっています。日本のメンタルヘルス分野を理解するには、日本の文化的な特異性を深く理解することが必要です。日本社会では、歴史的に精神疾患は偏見の対象とされ、しばしば無視されてきました。その結果、精神疾患の報告や治療が著しく不足する結果となっています。しかし、こうした障害は、より率直なコミュニケーションと偏見の解消を促す社会規範の変化や意識向上の取り組みによって、徐々に弱まりつつあります。日本政府は、メンタルヘルス問題への取り組みの緊急性を認識し、治療へのアクセスを向上させ、メンタルヘルスの向上を目的とした多くのプログラムを実施しています。 これらの取り組みは、メンタルヘルスを公衆衛生の必要性として最優先することの重要性を強調しており、メンタルヘルスサービスの拡大、労働者向けトレーニングプログラム、国民への啓発キャンペーンなどが含まれます。 技術の急速な発展に伴い、日本のメンタルヘルス業界では、デジタル技術を活用した創造的なソリューションが登場し始めています。こうした進歩は、装着可能なガジェットによる心理的兆候のモニタリングから遠隔療法プラットフォームまで多岐にわたっており、メンタルヘルスケアの提供における効果、コスト、アクセシビリティの改善につながる可能性があります。 注目すべき進歩にもかかわらず、日本のメンタルヘルス業界には、限られたリソース、熟練労働者の不足、根深い文化的信念など、多くの障害があります。しかし、これらの困難は創造性や異業種間の協力のチャンスでもあり、将来的にメンタルヘルスとフィジカルヘルスが同等に重視される時代への道筋をつけるものです。
ボナフィード・リサーチが発表した調査報告書「2029年の日本のメンタルヘルス市場の見通し」によると、日本のメンタルヘルス市場は2024年から2029年までに32億米ドルを超えると予測されています。日本のメンタルヘルス分野は近年、多くの注目すべき発展を遂げ、他の多くの国々とは一線を画しています。注目すべき傾向のひとつとして、厳しい労働文化や社会的要請など、日本特有の社会ストレスの解決に注目が集まっていることが挙げられます。その結果、こうしたニーズに対応する専門サービスの開発が進んでいます。さらに、オンラインカウンセリングプラットフォームやスマートフォンアプリの成長にみられるように、テクノロジーを駆使したメンタルヘルス治療の利用が増加しています。さらに、森林浴やマインドフルネスといった日本の伝統的なセラピー技術を主流のメンタルヘルス療法に取り入れることが高く評価されており、伝統的な手法と現代的な手法の融合が示されています。これらのパターンは、日本のメンタルヘルス市場が、その独特な文化的背景や社会問題の影響を受け、複雑かつ変化し続けていることを示しています。
個々の状況に応じて、治療戦略には、患者のニーズや文化的背景に合わせた投薬、カウンセリング、生活習慣の改善などが組み合わされることもあります。 また、日本では、危機ホットラインや移動式メンタルヘルスチームが緊急メンタルヘルスサービスを容易に利用できるようにしています。 深刻なメンタルヘルスの危機に直面した際には、これらのチームが迅速に対応し、すぐに支援や援助を提供します。 さらに、深刻な苦痛を経験している人に対しては、メンタル救急科のある病院が安定化と評価サービスを提供しています。日本では、通常、認定セラピストやカウンセラーがカウンセリング外来サービスを提供しており、クライアント中心の方法論に重点を置いています。これらのプログラムでは、文化的な感受性と守秘義務を重視しながら、精神的な問題について話し合うことができる安全な環境を提供しています。伝統的な日本の治療的アプローチは、カウンセリングセッションでは、現代的なエビデンスに基づく手順と組み合わされることがよくあります。在宅治療サービスは、通常のクリニックベースの治療を受けるのが難しい人向けに提供されています。患者の自宅で個別に治療計画を提供することで、これらのプログラムは継続的な治療を促し、メンタルヘルス支援を受けることへの偏見を軽減します。熟練した専門家が定期的に患者を訪問し、治療を行い、経過を観察します。入院治療サービスは、深刻な精神疾患により広範な支援を必要とする人々に対して包括的なケアを提供します。専門のメンタルヘルス施設では、薬物療法、心理療法、作業療法などの治療オプションが提供されます。多分野にわたる専門家チームが開発した個別治療プログラムの目標は、症状を安定させ、治癒を促すことです。
日本の小児精神医療では、子どもの幸福に影響を与える特定の文化的および社会経済的要因が考慮されています。日本の若者は、学業成績を重視する文化や同調圧力により、ストレスや不安の問題を抱えやすい傾向にあります。さらに、早期介入や治療は、精神衛生に関連するスティグマ(社会的烙印)により妨げられることがよくあります。そのため、子供たちが自分自身を表現し、文化的背景に適したケアを受けられる安全な場所の確立は、日本の小児精神保健サービスにおける最優先事項となっています。 これには、家族、学校、精神保健専門家の協力が不可欠です。 日本では、競争的な職場文化や文化的規範の要求が、大人の精神衛生に大きな影響を与えています。 長時間労働や職場でのストレスは、燃え尽き症候群やうつ病の発生率が高い要因となっています。さらに、若年成人は「ひきこもり」、つまり社会からの引きこもりを経験することが多く、社会統合やメンタルヘルスに問題が生じることもあります。 ストレスの多い現代社会において、包括的な治療の価値が認識される中、日本の成人向けメンタルヘルスサービスでは、これらの課題に対処するために、セラピー、職場支援プログラム、地域社会への働きかけを組み合わせた取り組みが行われています。 家族構造の変化と高齢化は、日本の高齢者向けメンタルヘルスサービスが直面する課題です。都市化や少子化などの要因により、高齢者は孤独や孤立に陥りやすく、それが認知症やうつ病などの精神疾患を悪化させる要因となっています。 さらに、家族は精神疾患の問題を家庭内で処理することを好む傾向があるため、文化的に理想とされる親孝行の精神が、専門家の支援を求めることを難しくしている可能性があります。高齢者の社会交流と精神衛生を促進するために、日本の老年精神保健サービスは、デイケアセンターや高齢者グループなどの地域社会を基盤とした支援ネットワークに重点を置いています。
日本では、統合失調症に苦しむ人の割合が非常に高く、統合失調症は通常、成人期初期に初めて発症します。妄想や幻覚は、社会生活や職業上のパフォーマンスに影響を与える一般的な症状です。治療には薬物療法や心理療法が用いられ、家族や地域社会の参加が重視されます。日本では、アルコール使用障害はあらゆる年齢層の人々に影響を与えていますが、中年層の人々に多く見られます。 高い発症率は、社会規範が公共の場での暴飲を頻繁に推奨しているという文化的影響に起因している可能性があります。 根本的な問題に対処するために、治療には医学的措置と文化的に特異的なカウンセリングの両方が含まれます。 日本では、双極性障害はあらゆる年齢層の人々に影響を与えており、典型的には後期の思春期または初期の成人期に発症します。この障害による気分の変動により、人間関係や日常生活が深刻な影響を受けることがあります。 症状をコントロールし再発を防ぐために、気分安定薬、カウンセリング、生活スタイルの改善が治療に一般的に用いられます。 うつ病は、ティーンエイジャーや高齢者を含むあらゆる年齢層の人々に影響を及ぼす一般的な精神疾患です。 文化によっては精神疾患に対する偏見があるため、治療を求めることをためらう人もいます。
治療法としては、薬物療法、カウンセリング、サポートグループなどが利用できます。日本文化における偏見の解消に向けた取り組みは、ますます重要性を増しています。不安障害は、あらゆる年齢の人々に影響を及ぼす幅広い疾患カテゴリーであり、過剰な心配や恐怖を伴うことがよくあります。職場や学業に対する期待は、症状を悪化させる可能性がある文化的ストレスの一例です。日本文化の規範や社会的な期待に特化したセラピー、薬物療法、ストレス軽減法は、いずれも治療の一環です。心的外傷後ストレス障害(PTSD)を抱える人は、恐ろしい経験や自然災害を経験した人であれば年齢を問いません。治療の選択肢や症状の現れ方は、文化的な影響を受ける可能性があります。従来の介入方法である外傷に焦点を当てたセラピーやサポートグループには、日本の伝統的な癒しのテクニックが頻繁に取り入れられています。日本では、薬物乱用障害は多くの年齢層に影響を及ぼす大きな問題となっており、特に思春期と社会人層がその影響を受けています。薬物乱用の発生率は、アルコールや薬物の使用に対する文化的見解や、社会経済的ストレスの影響を受けます。医療による解毒、カウンセリング、サポートグループは、いずれも治療プロセスの一部であり、被害軽減技術がますます重視されるようになっています。神経性無食欲症と神経性過食症は、あらゆる年齢層の人々を悩ませる摂食障害ですが、日本人を含むあらゆる年齢層の人々を悩ませる摂食障害ですが、10代と若い成人に最も多く見られます。 理想化された身体イメージの採用を迫られるなど、社会文化的要素が重要です。 家族の関与、食事カウンセリング、セラピーなどの多分野にわたる技術が、治療計画で一般的に使用されています。日本では、年齢層によってより多く見られる症状として、パーソナリティ障害、強迫性障害(OCD)、適応障害などがあります。
このレポートで取り上げる項目
• 歴史的な年:2018年
• 基準年:2023年
• 予測年:2024年
• 予測年:2029年
このレポートでカバーされている側面
• メンタルヘルス市場の見通しとその価値、予測、およびセグメント
• さまざまな推進要因と課題
• 進行中のトレンドと開発
• トップ企業プロフィール
• 戦略的提言
メンタルヘルス障害別
• うつ病
• 双極性障害
• 統合失調症
• 不安
• 外傷後ストレス障害(PTSD
• その他の精神障害
サービス別
• 入院治療サービス
• 居住治療サービス
• 外来治療サービス
• 緊急メンタルヘルスサービス
• その他のメンタルヘルスサービス
年齢層別
• 小児
• 成人
• 高齢者
レポートの手法:
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせた手法で構成されています。まず、市場を把握し、その市場に参入している企業をリストアップするために二次調査を実施しました。二次調査では、プレスリリース、企業の年次報告書、政府発行の報告書やデータベースなどの第三者情報源を活用しました。二次情報源からデータを収集した後、市場の主要関係者に対して電話インタビューを行い、市場の機能について調査し、市場のディーラーやディストリビューターに対して電話で問い合わせを行いました。その後、地域、階層、年齢層、性別などの観点から消費者層を均等にセグメントし、消費者に対する一次調査を開始しました。一次データを入手した後、二次情報源から得た詳細情報の検証を開始しました。
対象読者
本レポートは、メンタルヘルス業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者の方々の市場中心の戦略を調整する上で役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加えて、業界に関する競争上の知識も深めることができます。
目次
1. エグゼクティブサマリー
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2. 前提
2.3. 制限
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4. 報告書の作成、品質チェックおよび納品
4. 日本のマクロ経済指標
5.市場力学
5.1.市場の推進要因と機会
5.2.市場の抑制要因と課題
5.3.市場動向
5.3.1. XXXX
5.3.2. XXXX
5.3.3. XXXX
5.3.4. XXXX
5.3.5. XXXX
5.4. コロナウイルス(COVID-19)の影響
5.5. サプライチェーン分析
5.6. 政策および規制の枠組み
5.7. 業界専門家による見解
6. 日本のメンタルヘルス市場の概要
6.1.市場規模(金額
6.2.市場規模と予測、メンタルヘルス障害別
6.3.市場規模と予測、サービス別
6.4.市場規模と予測、その他のメンタルヘルスサービス別
7. 日本のメンタルヘルス市場の区分
7.1. 日本のメンタルヘルス市場:精神疾患別
7.1.1. 日本のメンタルヘルス市場規模:うつ病別、2018年~2029年
7.1.2. 日本のメンタルヘルス市場規模:双極性障害別、2018年~2029年
7.1.3. 日本のメンタルヘルス市場規模、統合失調症別、2018年~2029年
7.1.4. 日本のメンタルヘルス市場規模、不安障害別、2018年~2029年
7.1.5. 日本のメンタルヘルス市場規模、心的外傷後ストレス障害(PTSD)およびその他別、2018年~2029年
7.2. 日本のメンタルヘルス市場、サービス別
7.2.1. 日本のメンタルヘルス市場規模、入院治療サービス別、2018年~2029年
7.2.2. 日本のメンタルヘルス市場規模、居住型治療サービス別、2018年~2029年
7.2.3. 日本のメンタルヘルス市場規模、外来治療サービス別、2018年~2029年
7.2.4. 日本メンタルヘルス市場規模、救急メンタルヘルスサービス別、2018年~2029年
7.2.5. 日本メンタルヘルス市場規模、その他メンタルヘルスサービス別、2018年~2029年
7.3. 日本メンタルヘルス市場、その他メンタルヘルスサービス別
7.3.1. 日本メンタルヘルス市場規模、小児向け、2018年~2029年
7.3.2. 日本のメンタルヘルス市場規模、成人向け、2018年~2029年
7.3.3. 日本のメンタルヘルス市場規模、高齢者向け、2018年~2029年
8. 日本のメンタルヘルス市場機会評価
8.1. メンタルヘルス障害別、2024年~2029年
8.2. サービス別、2024年から2029年
8.3. その他のメンタルヘルスサービス別、2024年から2029年
9. 競合状況
9.1. ポーターのファイブフォース
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 企業概要
9.2.1.2. 企業概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地域別洞察
9.2.1.5. 事業セグメントおよび業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 経営陣
9.2.1.8. 戦略的動きおよび開発
9.2.2. 企業 2
9.2.3. 企業 3
9.2.4. 企業 4
9.2.5. 企業 5
9.2.6. 企業 6
9.2.7. 企業 7
9.2.8. 企業 8
10. 戦略的提言
11. 免責条項
図表一覧
図1:日本のメンタルヘルス市場規模(2018年、2023年、2029年予測)(単位:百万米ドル)
図2:メンタルヘルス障害別市場魅力度指数
図3:サービス別市場魅力度指数
図4:その他のメンタルヘルスサービス別市場魅力度指数
図5:日本のメンタルヘルス市場のポーターのファイブフォース
表の一覧
表1:メンタルヘルス市場に影響を与える要因、2023年
表2:日本のメンタルヘルス市場規模および予測、メンタルヘルス障害別(2018年~2029年予測)(単位:百万米ドル
表3:日本のメンタルヘルス市場規模および予測、サービス別(2018年~2029年予測)(単位:百万米ドル
表4:日本のメンタルヘルス市場規模および予測、その他のメンタルヘルスサービス別(2018年~2029年予測)(単位:百万米ドル)
表5:日本のうつ病のメンタルヘルス市場規模(2018年~2029年)(単位:百万米ドル)
表6:日本におけるメンタルヘルス市場の双極性障害の規模(2018年~2029年) (単位:百万米ドル
表7:日本におけるメンタルヘルス市場の統合失調症の規模(2018年~2029年) (単位:百万米ドル
表8:日本におけるメンタルヘルス市場の不安障害の規模(2018年~2029年) (単位:百万米ドル
表9:日本における心的外傷後ストレス障害(PTSD)およびその他の精神疾患の市場規模(2018年~2029年)
表10:日本における入院治療サービスの市場規模(2018年~2029年)
表11:日本における居住型治療サービスの市場規模(2018年~2029年)
表12:日本のメンタルヘルス市場における外来治療サービス(2018年~2029年)の市場規模(単位:百万米ドル)
表13:日本のメンタルヘルス市場における緊急メンタルヘルスサービス(2018年~2029年)の市場規模(単位:百万米ドル)
表14:日本のメンタルヘルス市場におけるその他のメンタルヘルスサービス(2018年~2029年)の市場規模(単位:百万米ドル)
表15:日本のメンタルヘルス市場における小児向けサービス(2018年~2029年)の規模(単位:百万米ドル)
表16:日本のメンタルヘルス市場における成人向けサービス(2018年~2029年)の規模(単位:百万米ドル)
表17:日本のメンタルヘルス市場における高齢者向けサービス(2018年~2029年)の規模(単位:百万米ドル)
According to the research report, " Japan Mental Health Market Outlook, 2029," published by Bonafide Research, the Japan Mental Health market is anticipated to add to more than USD 3.2 Billion by 2024–29. Japan's mental health sector has experienced a number of notable developments in recent years that have set it apart from many other nations. One notable trend is the increased attention being paid to resolving Japanese-specific societal stresses, such the demanding work culture and social demands, which has resulted in the development of specialised services catered to these requirements. Furthermore, Japan has witnessed a rise in the use of technology in mental health treatment, as evidenced by the growth of online counselling platforms and smartphone applications that appeal to the country's tech-savvy populace. Furthermore, incorporating traditional Japanese therapeutic techniques like forest bathing and mindfulness into mainstream mental health therapies is highly valued, demonstrating a fusion of traditional and modern methods. These patterns point to a complex and changing market environment for mental health in Japan, which is influenced by the country's unique cultural setting and social issues.
Depending on the particular condition, treatment strategies may involve a mix of medication, counselling, and lifestyle changes catered to the requirements and cultural background of the patient. Crisis hotlines and mobile mental health teams make emergency mental health services easily available in Japan. When faced with an acute mental health crisis, these teams act quickly to offer support and assistance right away. Furthermore, for those experiencing severe distress, hospitals with mental emergency departments provide stabilisation and evaluation services. In Japan, outpatient counselling services are usually offered by certified therapists or counsellors and place a strong emphasis on a client-centered methodology. These programmes put an emphasis on cultural sensitivity and confidentiality while providing a secure environment in which people may discuss their mental health issues. Traditional Japanese therapeutic approaches are frequently combined with contemporary, evidence-based procedures in counselling sessions. Home-based treatment services are intended for those who might have trouble getting access to standard clinic-based therapy. By providing individualised treatment plans in the convenience of the patient's own home, these programmes encourage continuity of care and lessen the stigma attached to seeking mental health assistance. Skilled practitioners conduct routine client visits, delivering therapeutic treatments and tracking advancements. Inpatient hospital treatment services in Japan provide all-encompassing care for people who need extensive assistance due to serious mental health issues. Treatment options offered by specialised mental health facilities include pharmaceutical administration, psychotherapy, and occupational therapy. The goal of individualised treatment programmes developed by multidisciplinary teams is to stabilise symptoms and encourage healing.
Paediatric mental health care in Japan takes into account the particular cultural and socioeconomic elements that have an impact on children's wellbeing. Japanese youngsters are susceptible to stress and anxiety problems due to the culture's emphasis on academic achievement and peer pressure. Furthermore, early intervention and treatment are frequently hampered by the stigma associated with mental health. As a result, the establishment of safe places for kids to express themselves and get care that is appropriate to their cultural background is a top priority for paediatric mental health services in Japan. This frequently entails cooperation between families, schools, and mental health specialists. In Japan, the demands of a competitive workplace culture and cultural norms have a significant impact on adult mental health. Extensive work hours and stress from the workplace are factors in the high incidence of burnout and depression. Furthermore, young adults frequently experience "hikikomori," or social withdrawal, which can cause difficulties with social integration and mental health. Recognising the value of comprehensive treatment in a high-pressure world, adult mental health services in Japan combine therapy, workplace assistance programmes, and community outreach initiatives to address these challenges. A shifting family structure and an ageing population are the challenges facing Japan's geriatric mental health services. Due to factors like urbanisation and falling birth rates, elderly people frequently face loneliness and isolation, which exacerbates mental health conditions like dementia and depression. Furthermore, because families may prefer to handle mental health issues within the home, the cultural ideal of filial piety may make it difficult for people to seek professional assistance. In order to encourage social interaction and mental health among the older population, geriatric mental health services in Japan concentrate on community-based networks of assistance, such as day care centres and senior citizen groups.
A large percentage of people in Japan suffer from schizophrenia, which usually first appears in early adulthood. Delusions and hallucinations are common symptoms that affect social and professional performance. Medication and therapy are used in treatment, with an emphasis on family and community participation. Among Japan, alcohol use disorders affect people of all ages, although they are more common among middle-aged people. The high incidence may be attributed to cultural influences, since social norms frequently encourage binge drinking in public. In order to address underlying difficulties, treatment consists of both medical measures and culturally specific counselling. In Japan, bipolar disorder affects people of all ages, with late adolescence or early adulthood being the typical time of start. Relationships and daily living can be seriously disrupted by the disorder's mood swings. Mood stabilisers, counselling, and lifestyle modifications are commonly used in treatment to control symptoms and avoid recurrence. Depression is a common mental health issue that affects people of all ages, including teenagers and the elderly Japaneese people. The stigma associated with mental illness in some cultures may prevent people from seeking care.
Medication, counselling, and support groups are available as forms of treatment; destigmatization initiatives within Japanese culture are becoming more and more important. Anxiety disorders are a broad category of illnesses that impact people of all ages and are frequently typified by excessive worry and dread. Workplace and academic expectations are examples of cultural stresses that might worsen symptoms. Therapy, medicine, and stress-reduction methods specific to Japanese cultural norms and social expectations are all part of the treatment. There are people with Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) might be of any age, although those who have gone through terrible experiences or natural disasters. Treatment choices and symptom manifestation may be influenced by cultural influences. Traditional Japanese healing techniques are frequently included into trauma-focused therapy and support groups, which are conventional interventions. Adolescents and working adults are among the many age groups affected by substance abuse disorders, which are a major problem in Japan. The incidence of substance misuse is influenced by cultural views towards alcohol and drug usage as well as socioeconomic stresses. Medical detoxification, counselling, and support groups are all part of the treatment process, with a growing emphasis on harm reduction techniques. Anorexia nervosa and bulimia nervosa are two eating disorders that can afflict people of all ages, including Japanese people, but they are most common in teenagers and young adults. Sociocultural elements are important, such as the push to adopt idealised body images. Multidisciplinary techniques, such as family engagement, dietary counselling, and therapy, are commonly used in treatment plans. There are several conditions that are more common in different age groups in Japan include personality disorders, obsessive-compulsive disorder (OCD), and adjustment problems.
Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029
Aspects covered in this report
• Mental Health market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation
By Mental Health Disorder
• Depression
• Bipolar Disorder
• Schizophrenia
• Anxiety
• Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)
• Other Mental Disorders
By Services
• Inpatient Treatment Services
• Residential Treatment Services
• Outpatient Treatment Services
• Emergency Mental Health Services
• Other Mental Health Services
By Age Group
• Paediatric
• Adult
• Geriatric
The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.
Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Mental Health industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.
