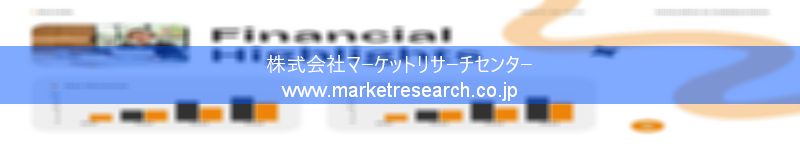| • レポートコード:BONA5JA-0213 • 出版社/出版日:Bonafide Research / 2024年7月 • レポート形態:英文、PDF、67ページ • 納品方法:Eメール • 産業分類:IT&通信 |
| Single User(1名様閲覧用、印刷不可) | ¥418,000 (USD2,750) | ▷ お問い合わせ |
| Corporate License(閲覧人数無制限、印刷可) | ¥798,000 (USD5,250) | ▷ お問い合わせ |
• お支払方法:銀行振込(納品後、ご請求書送付)
レポート概要
日本の遠隔医療市場は、技術の進歩、行政の変化、医療サービスのニーズによって、本質的に発展してきました。1980年代から1990年代にかけて、日本は主にビデオ会議技術を活用した遠隔医療相談や臨床研修に焦点を当てた調査やパイロットプロジェクトを通じて、遠隔医療の研究を開始しました。2000年代には、さらに発達したウェブや携帯通信により、関心がさらに広がりました。2009年には厚生労働省が遠隔医療に関するルールを定め、特定の状況下、特に遠隔地での遠隔医療を認めるようになりました。2011年の東日本大震災では、災害時の遠隔医療の重要性が浮き彫りになり、その普及が加速しました。2015年には、公共機関が遠隔医療の規則を拡大し、その後の議論や常習的な病気を経営陣に組み込みました。2018年の別の返済システムの発表により、明確な条件での初期の議論をカバーすることで、遠隔医療がさらに支援されました。2020年のパンデミックにより、感染伝播のリスクを制限するために、公共機関が一時的にすべての患者の初期会議を遠隔医療で許可したため、遠隔医療の利用が急増しました。これにより、全国的に急速に受け入れられるようになりました。最近登場したものとしては、プライム会員向けのAmazonのOne Clinical、GNCのバーチャル診療管理、およびWalgreensのバーチャルヘルスケアによるリクエストベースの診察や薬の処方などがあります。これらの発表は、市場のポジティブな方向性を意味し、世界中の人々の高まる医療サービスニーズに一致する強力な場面を反映しています。日本の遠隔医療市場で事業を展開する主な企業には、NTTデータ、NEC、富士通、パナソニック、東芝、エムスリー、ソニー、日立製作所、オリンパスなどがあります。
Bonafide Researchが発表した調査レポート「日本遠隔医療市場の見通し、2029年」によると、日本の遠隔医療市場は2024年から2029年までに60億米ドル以上に達すると予測されています。 高齢者人口の増加は、国内市場の成長を促進する主な要因のひとつです。遠隔医療は、糖尿病、高血圧、心臓病、関節炎などの症状を、バイタルサイン、服薬状況、症状の進行状況を追跡することで遠隔でモニタリングするために広く利用されています。これに加えて、高速インターネット接続や革新的な医療機器など、国内における最先端技術の成長と発展が遠隔相談やモニタリングを促進しており、これも成長を促す要因となっています。さらに、デジタルヘルスソリューションの採用を促進するための日本政府によるさまざまな取り組みの実施が、市場成長を後押ししています。日本政府による遠隔医療の利用促進の取り組み、高齢化、医療従事者不足により、日本の遠隔医療市場は今後数年間で大幅に成長すると予想されています。また、5GやAIなどの技術進歩により、より高度な遠隔医療サービスの提供が可能になることも、市場の成長につながると期待されています。日本では、遠隔医療プラットフォームと電子カルテ(EHR)を統合し、医療の継続性を高めることで、医療従事者が遠隔相談中に患者の病歴や医療情報にアクセスできるようにすることが、市場の成長に好影響を与えています。研究開発(R&D)への注力の強化、個別化医療の需要の高まり、ウェルネスと予防医療への重点の強化、急速な都市化など、その他の要因も市場に有益な成長機会をもたらしています。
日本の遠隔医療におけるソフトウェアおよびサービス分野は、現在、いくつかの主な理由により成長を続けています。遠隔医療におけるソフトウェアソリューションは、患者情報の継続的な組み合わせ、遠隔会議での作業、日本向けに明確に定義された管理基準との整合性を保証します。遠隔医療に関連するサービス、例えば仮想患者管理段階や遠隔相談プログラムなどは、特に実際の医療体制が限られている農村地域において、医療サービスの可用性を向上させる能力があるため、需要が高まっています。また、コロナウイルスのパンデミックにより、遠隔医療の導入が加速し、この分野のイニシアチブがさらに強化されました。ソフトウェア主導の遠隔医療システムの利便性、コスト効率、および性能は、医療サービス提供者、患者、および政策立案者から大きな支持を得ています。日本の遠隔医療におけるハードウェア分野は急速に成長していますが、市場シェアに関しては、製品およびサービス分野にまだ及びません。遠隔医療に不可欠な機器には、遠隔検査機器、遠隔医療用スタンド、医療現場向けにカスタマイズされたビデオ会議機器などの医療用機器が含まれます。この分野の発展は、継続的な機械の進歩、医療サービスのデジタル化への取り組みの拡大、医療サービス提供者や政府機関による遠隔医療システムへの関心の高まりによって推進されています。しかし、実際には、複雑な導入費用など、さまざまな課題が存在しており、ソフトウェア主導の他のオプションと比較して、機器主導の遠隔医療システムの広範な普及を制限しています。
リアルタイム遠隔医療は、いくつかの説得力のある理由により、日本では主要な分野として際立っています。現在進行中の遠隔医療の取り組みは、医療サービス提供者と患者間の迅速かつ直接的な連携を可能にし、簡潔な結論、治療の選択肢、患者の状況の継続的な確認を実現しています。この能力は、適切な介入が患者の治療結果に完全に影響を与える可能性がある危機的な状況において、特に重要です。さらに、継続的な遠隔医療の段階では、ビデオ会議、安全な情報提供、電子化された健康記録の連携といった要素が提供され、医療提供者と患者の両方の利便性と効率性が向上します。また、日本国内のさまざまな医療現場で継続的な遠隔医療の受け入れを促進する行政支援や償還戦略により、この分野の権限はさらに強化されています。遠隔患者モニタリング(RPM)は、日本の遠隔医療市場で急速に成長している分野です。遠隔患者モニタリングには、従来の医療サービス環境を超えて、患者の健康状態を遠隔から監視するための臨床機器や技術の利用が含まれます。この分野の成長は、ウェアラブル健康機器の進歩、継続的な検査を必要とする持病の蔓延、そして遠隔医療サービス全般の恩恵を受ける日本の高齢者人口の増加といった要因によって促進されています。RPM システムは、重要な兆候、服薬遵守、その他の健康指標に関する継続的な情報収集を提供し、医療問題の早期発見と医療サービス提供者による積極的な介入を可能にします。この分野の成長は、診療所への来院回数の減少、持続的な成果の追求、遠隔モニタリングシステムによる医療費の削減を目的とした医療サービスの改革によっても支えられています。
医療サービス供給者は、医療サービス提供を促進し、遠隔医療の受容を推進するという重要な役割を担っているため、日本の遠隔医療市場における主要な部分を占めています。彼らは、患者ケアの向上、医療アクセスの拡大、資源配分の改善を目的とした遠隔医療ソリューションの最前線に立っています。医療クリニック、センター、個人専門家を含む医療サービスプロバイダーは、遠隔地や医療過疎地域への対応範囲の拡大、患者の待ち時間の短縮、機能効率の向上により、遠隔医療の恩恵を受けています。日本の遠隔医療市場における発展途上の課題は、基本的には、有益な医療給付に対する購買者の関心の高まりと、臨床的専門知識へのアクセス向上によって決定されます。人口の高齢化、持病の蔓延、日本在住者の機械的熟練度といった要因が、遠隔医療に対する患者の関心を刺激しています。患者は、自宅にいながら医療サービスを受けられるという利便性から、遠隔医療を高く評価しています。特に高齢者や身体障害者にとっては、非常に有益です。この分野の発展は、使いやすいインターフェースと安全な通信ステーションを提供するモバイル技術と遠隔医療の進歩によっても支えられています。日本の遠隔医療市場のその他のセグメントには、保険者とその他が含まれます。保険者には、保険代理店、政府医療事業、および医療給付と遠隔医療会議の費用を負担する雇用主が含まれます。保険者は、医療供給者による遠隔医療の受容や患者による受容に影響を与える支払い戦略、組み込みモデル、金銭的インセンティブに影響を与えるため、極めて重要なパートナーです。その他には、技術サプライヤー、メディア配信企業、基盤整備、情報セキュリティの整合性、戦略推進など、日本の遠隔医療環境の整備を支援する行政機関などの下位パートナーが含まれます。
このレポートで考察されている事項
• 歴史的な年:2018年
• 基準年:2023年
• 予測年:2024年
• 予測年:2029年
このレポートでカバーされている事項
• 遠隔医療市場の見通しとその価値、予測、およびセグメント
• さまざまな推進要因と課題
• 進行中のトレンドと開発
• トップ企業プロフィール
• 戦略的提言
サービス別
• ソリューション
• コンポーネント別
• ソフトウェア & サービス
• ハードウェア
製品タイプ別
• リアルタイム遠隔医療
• 遠隔患者モニタリング
エンドユーザー別
• 医療サービス提供者
• 患者
• 保険者
• その他
レポートの手法:
このレポートは、一次調査と二次調査を組み合わせた手法で構成されています。まず、市場を把握し、その市場に参入している企業をリストアップするために二次調査を実施しました。二次調査では、プレスリリース、企業の年次報告書、政府発行の報告書やデータベースなどの第三者情報源を活用しました。二次情報源からデータを収集した後、市場の主要関係者に対して電話インタビューを行い、市場の機能について調査し、市場のディーラーや販売代理店に対して電話で問い合わせを行いました。その後、地域、階層、年齢層、性別などの観点から消費者層を均等にセグメントし、消費者に対する電話調査を開始しました。一次データを入手した後、二次情報源から得た詳細情報の検証を開始しました。
対象読者
このレポートは、遠隔医療業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者の方々の市場中心の戦略を調整する上で役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加えて、業界に関する競争上の知識も深めることができます。
目次
1. エグゼクティブサマリー
2.市場構造
2.1.市場考察
2.2. 前提
2.3. 制限
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4. 報告書の作成、品質チェック、納品
4. 日本のマクロ経済指標
5.市場力学
5.1.市場の推進要因と機会
5.2.市場の抑制要因と課題
5.3.市場動向
5.3.1. XXXX
5.3.2. XXXX
5.3.3. XXXX
5.3.4. XXXX
5.3.5. XXXX
5.4. コロナウイルス(COVID-19)の影響
5.5. サプライチェーン分析
5.6. 政策および規制の枠組み
5.7. 業界専門家による見解
6. 日本遠隔医療市場の概要
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.市場規模と予測(コンポーネント別
6.3.市場規模と予測(製品タイプ別
6.4.市場規模と予測(エンドユーザー別
6.5. 地域別市場規模と予測
7. 日本遠隔医療市場のセグメント
7.1. 日本遠隔医療市場、コンポーネント別
7.1.1. 日本遠隔医療市場規模、ソフトウェアおよびサービス別、2018年~2029年
7.1.2. 日本遠隔医療市場規模、ハードウェア別、2018年~2029年
7.2. 日本遠隔医療市場、製品タイプ別
7.2.1. 日本遠隔医療市場規模、リアルタイム遠隔医療別、2018年~2029年
7.2.2. 日本遠隔医療市場規模、遠隔患者モニタリング別、2018年~2029年
7.3. 日本遠隔医療市場、エンドユーザー別
7.3.1. 日本遠隔医療市場規模、医療サービス提供者別、2018年~2029年
7.3.2. 日本遠隔医療市場規模、患者別、2018年~2029年
7.3.3. 日本遠隔医療市場規模、支払者別、2018年~2029年
7.3.4. 日本遠隔医療市場規模、その他別、2018年~2029年
7.4. 日本遠隔医療市場、地域別
7.4.1. 日本遠隔医療市場規模、北部別、2018年~2029年
7.4.2. 日本遠隔医療市場規模、東部別、2018年~2029年
7.4.3. 日本遠隔医療市場規模、西日本、2018年~2029年
7.4.4. 日本遠隔医療市場規模、南日本、2018年~2029年
8. 日本遠隔医療市場機会評価
8.1. コンポーネント別、2024年~2029年
8.2. 製品タイプ別、2024年から2029年
8.3. エンドユーザー別、2024年から2029年
8.4. 地域別、2024年から2029年
9. 競合状況
9.1. ポーターのファイブフォース
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 企業概要
9.2.1.2. 企業概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントおよび業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 経営陣
9.2.1.8. 戦略的動きおよび開発
9.2.2. 企業 2
9.2.3. 企業 3
9.2.4. 企業 4
9.2.5. 企業 5
9.2.6. 企業 6
9.2.7. 企業 7
9.2.8. 企業 8
10. 戦略的提言
11. 免責条項
図表リスト
図1:日本の遠隔医療市場規模(2018年、2023年、2029年予測)(単位:百万米ドル)
図2:コンポーネント別市場魅力度指数
図3:市場魅力度指数、製品タイプ別
図4:市場魅力度指数、エンドユーザー別
図5:市場魅力度指数、地域別
図6:日本の遠隔医療市場におけるポーターのファイブフォース
表一覧
表1:2023年の遠隔医療市場に影響を与える要因
表2:日本遠隔医療市場規模および予測、コンポーネント別(2018年~2029年予測)(単位:百万米ドル)
表3:日本遠隔医療市場規模および予測、製品タイプ別(2018年~2029年予測)(単位:百万米ドル)
表4:日本遠隔医療市場規模および予測、エンドユーザー別(2018年~2029年予測)(単位:百万米ドル)
表5:日本遠隔医療市場規模および予測、地域別(2018年~2029年予測)(単位:百万米ドル)
表6:日本遠隔医療市場規模、ソフトウェアおよびサービス(2018年~2029年)(単位:百万米ドル)
表7:日本遠隔医療市場規模(2018年~2029年)ハードウェア(単位:百万米ドル)
表8:日本遠隔医療市場規模(2018年~2029年)リアルタイム遠隔医療(単位:百万米ドル)
表9:日本遠隔医療市場規模(2018年~2029年)遠隔患者モニタリング(単位:百万米ドル)
表10:日本遠隔医療市場規模(2018年~2029年)医療プロバイダー(単位:百万米ドル
表11:日本遠隔医療市場規模(2018年~2029年)患者(単位:百万米ドル
表12:日本遠隔医療市場規模(2018年~2029年)支払者(単位:百万米ドル
表13:日本の遠隔医療市場規模(その他)(2018年~2029年)単位:百万米ドル
表14:日本の遠隔医療市場規模(北日本)(2018年~2029年)単位:百万米ドル
表15:日本の遠隔医療市場規模(2018年~2029年)東部(単位:百万米ドル)
表16:日本の遠隔医療市場規模(2018年~2029年)西部(単位:百万米ドル)
表17:日本の遠隔医療市場規模(2018年~2029年)南部(単位:百万米ドル)
According to the research report, "Japan Telemedicine Market Outlook, 2029," published by Bonafide Research, the Japan telemedicine market is anticipated to add to more than USD 6 Billion by 2024–29. The rising geriatric population is one of the key factors driving the market growth in the country. Telemedicine is widely used to remotely monitor conditions such as diabetes, hypertension, heart disease, and arthritis by tracking vital signs, medication adherence, and symptom progression. Besides this, the growth and development of cutting-edge technology in the country, such as high-speed internet connections and innovative medical devices, facilitate remote consultations and monitoring, is acting as another growth-inducing factor. Moreover, the implementation of various initiatives by the Japanese government to encourage the adoption of digital health solutions is favoring the market growth. The telemedicine market in Japan is expected to grow significantly in the coming years due to the government's efforts to promote the use of telemedicine, the aging population, and the shortage of healthcare professionals. The market is also expected to benefit from technological advancements, such as 5G and AI, which are making it possible to provide more advanced telemedicine services. In Japan, the integration of telemedicine platforms with electronic health records (EHR) to enhance the continuity of care, enabling healthcare providers to have access to patient histories and medical information during remote consultations, is positively influencing the market growth. Other factors, including an enhanced focus on research and development (R&D), increasing demand for personalized healthcare delivery, rowing emphasis on wellness and preventive healthcare, and rapid urbanization, are providing remunerative growth opportunities for the market.
The Software & Services fragment in Japanese telemedicine is presently driving because of a few key reasons. Software solutions in telemedicine empower consistent combination of patient information, work with distant meetings, and guarantee consistence with administrative norms well defined for Japan. Services related with telemedicine, like virtual patient administration stages and teleconsultation programming, are sought after because of their capacity to improve medical services availability, particularly in rustic regions with restricted actual medical care framework. Also, the Coronavirus pandemic sped up the reception of telemedicine arrangements, further hardening the initiative of this fragment. The comfort, cost-adequacy, and proficiency of programming driven telemedicine arrangements have earned huge help from medical care suppliers, patients, and policymakers the same. The Hardware fragment inside Japanese telemedicine is encountering strong development yet has not yet outperformed the Product and Administrations portion with regards to showcase authority. Equipment parts fundamental for telemedicine incorporate clinical gadgets like remote checking hardware, telehealth stands, and video conferencing instruments customized for medical care settings. The development in this section is driven by continuous mechanical headways, expanding medical services digitization endeavors, and rising interests in telehealth framework by medical care suppliers and government bodies. Nonetheless, difficulties, for example, high introductory expenses joining intricacies actually exist, which limit the far reaching reception of equipment driven telemedicine arrangements contrasted with programming driven other options.
Real-time telemedicine stands apart as the main section in Japan because of a few convincing reasons. Ongoing telemedicine arrangements empower quick and direct cooperation between medical services suppliers and patients, working with brief conclusion, therapy choices, and ceaseless checking of patient circumstances. This ability is especially essential in crisis circumstances where ideal mediation can altogether affect patient results. In addition, constant telemedicine stages offer elements like video discussions, secure informing, and computerized wellbeing record coordination, upgrading comfort and proficiency for both medical care suppliers and patients. The fragment's authority is additionally reinforced by administrative help and repayment strategies that advance the reception of continuous telemedicine arrangements across different medical care settings in Japan. Remote Patient Monitoring (RPM) is a quickly developing fragment inside the Japanese telemedicine market. Remote Patient Monitoring includes the utilization of clinical gadgets and innovation to screen patients' wellbeing from a distance, beyond conventional medical services settings. This portion's development is driven by a few variables, remembering headways for wearable wellbeing gadgets, expanding pervasiveness of constant sicknesses requiring consistent checking, and a developing old populace in Japan that advantages from far off medical services the board arrangements. RPM arrangements offer nonstop information assortment on essential signs, drug adherence, and other wellbeing measurements, empowering early recognition of medical problems and proactive mediation by medical care suppliers. The fragment's extension is likewise upheld by medical services changes pointed toward decreasing clinic visits, working on persistent results, and bringing down medical services costs through remote observing arrangement.
Healthcare Suppliers stand as the main fragment in Japan's telemedicine market because of their critical job in conveying healthcare services administrations and driving telemedicine reception. They are at the front of executing telemedicine answers for upgrade patient consideration, further develop medical care availability, and enhance asset allotment. Medical services suppliers, including medical clinics, centers, and individual experts, benefit from telemedicine by extending their compass to remote or underserved regions, decreasing patient stand by times, and expanding functional effectiveness. Patients address a developing fragment inside Japan's telemedicine market, basically determined by expanding buyer interest for helpful medical care benefits and upgraded admittance to clinical mastery. Factors like the maturing populace, rising constant sickness pervasiveness, and mechanical proficiency among Japanese residents have energized patient interest in telemedicine. Patients esteem telemedicine for its benefit, permitting them to get to medical services from the solace of their homes, especially advantageous for old or versatility impeded people. The development of this portion is additionally upheld by progressions in versatile innovation and telehealth stages that offer easy to use interfaces and secure correspondence stations, guaranteeing patient secrecy and fulfilment. The excess sections in Japan's telemedicine market incorporate Payers and Others. Payers incorporate insurance agency, government medical care projects, and bosses who finance medical care benefits and repay telemedicine conferences. Payers are pivotal partners as they impact repayment strategies, inclusion models, and monetary motivations that influence telemedicine reception by medical care suppliers and acknowledgment by patients. Others allude to subordinate partners, for example, innovation suppliers, media transmission organizations, and administrative bodies engaged with foundation improvement, information security consistence, and strategy promotion to help the telemedicine environment in Japan.
Considered in this report
• Historic year: 2018
• Base year: 2023
• Estimated year: 2024
• Forecast year: 2029
Aspects covered in this report
• Telemedicine market Outlook with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation
By Offering
• Solution
• By Component
• Software & Services
• Hardware
By Product Type
• Real-time Telemedicine
• Remote Patient Monitoring
By End-User
• Healthcare Providers
• Patients
• Payers
• Others
The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary and secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and list the companies that are present in it. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual reports of companies, and government-generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources, primary research was conducted by conducting telephone interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducting trade calls with dealers and distributors of the market. Post this; we have started making primary calls to consumers by equally segmenting them in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us, we can start verifying the details obtained from secondary sources.
Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations, and organizations related to the Telemedicine industry, government bodies, and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing and presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.