日本の海上安全システム市場規模(~2029年)

| 本報告書は、日本の海上安全システム市場に関する包括的な分析を提供しております。市場の構造、ダイナミクス、機会、競争環境などが詳細に検討されています。 まず、要旨として市場の全体像が示され、その後市場構造についての考察が行われます。市場の前提条件や制限事項、使用される略語、情報源、定義、地理的な視点についても触れられています。 調査方法としては、二次調査と一次データ収集が行われ、市場形成とその検証がなされています。また、報告書の作成に際しては品質チェックが行われ、最終的な納品がなされます。 次に、日本のマクロ経済指標が提示され、市場のダイナミクスが分析されます。市場促進要因や機会、阻害要因、課題、トレンドについても詳しく述べられ、コビッド19の影響やサプライチェーンの分析、政策及び規制の枠組みについても考察されています。 日本の海上安全システム市場の概要として、市場規模や予測がコンポーネント別、システム別、エンドユーザー別、地域別に示されています。これにより、各カテゴリにおける市場の動向が明らかにされます。 市場セグメントについては、コンポーネント、システム、エンドユーザー別に市場規模が分析され、地域別のデータも提供されています。これにより、各地域における市場の成長機会が評価されています。 競争環境のセクションでは、ポーターの5つの力を用いて市場の競争状況が分析され、主要企業のプロフィールが紹介されています。各企業の概要、財務ハイライト、地理的洞察、事業セグメントと業績、製品ポートフォリオ、主要役員、戦略的な動きについて情報が提供されています。 最後に、戦略的提言が行われ、今後の市場動向に関する示唆が与えられています。また、免責事項についても言及されており、情報の使用に関する注意点が示されています。 このように、本報告書は日本の海上安全システム市場に関する多面的なアプローチを提供し、関係者に対して価値ある情報を提供しております。 |
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
海岸線が3万キロメートル以上あり、国内総生産に占める海事産業の割合が大きい日本では、経済競争力と海の安全を維持するために、包括的な海上安全システムが必要です。日本の海上安全システムに責任を負う堂々たる規制の枠組みには、海上保安庁や国土交通省などの重要な政府機関が含まれます。これらの機関は、海上交通安全に関する法律、港湾規制に関する法律、海洋汚染防止法などを施行します。これらの機関は、少なくともSOLASやMARPOLのような国際条約の範囲内で、また責任を持って業務を遂行できるようにすることで、規制を定め、海洋環境の保護と安全をさらに守っています。日本は、海上安全システムにおいて最先端の技術を大いに導入してきました。船舶の動静を監視・制御し、衝突の回避や交通渋滞の回避に大きく貢献しているのは、船舶交通サービスと自動識別システムです。日本の準天頂衛星システムは、非常に正確な測位信号を提供し、船舶の安全航行と円滑な運航に貢献しています。この場合、これらの技術は状況認識と運航の有効性を高める上で非常に重要になります。海上保安庁は、最新鋭の船舶、航空機、通信手段によって、捜索救助活動の最前線に立っています。日本の海上交通管理システムは、混雑した海域で対向する交通の流れを分離するためのTSSを提供し、それによって衝突の発生を減少させます。港湾国家管理は、安全および環境に関する国際基準に適合していることを確認するため、外国船舶の検査を規定しています。これは、多忙な日本の港湾や水路における海上交通の安全かつ効率的な通行のために非常に重要な措置です。
Bonafide Researchが発行した調査レポート「日本の海上安全システム市場の概要、2029年」によると、日本の海上安全システム市場は2023年に20億米ドル以上と評価されています。日本の海上安全システムには、保険とリスク管理が含まれています。海上保険市場では、偶然の事故による損失、貨物損失、環境負債など、特定の種類のリスクをカバーするための商品を提供することができます。リスク評価には洗練されたツールや方法論があり、こうした海上のリスクをより適切に評価し、効率的に軽減するのに役立ちます。包括的なリスク管理戦略は、海事全般の安全性を高めながら、利害関係者の利益を確保することができます。海事部門は日本のGDPの主要な収入源であり、経済的な安定と成長を確保するためには高い安全基準を確立する必要があります。また、海運、ロジスティクス、技術開発などの分野で、大量の雇用機会も生み出しています。海上安全への配慮は、安全性と運航効率の向上を目指す取り組みへの継続的な投資と支援努力を開始する上で重要です。国際協力は、日本の海上安全システムにおいて不可欠な部分を形成しています。近隣諸国や諸機関との二国間協定や多国間協定は、海上の安全とセキュリティを強化します。日本は、国際海事機関(IMO)のような海事関連のあらゆる国際機関に積極的に参加し、世界と比較した場合の日本の安全対策の一貫性を実現しています。これにより、それぞれの国の海事に関する共通の問題に直面し、世界的な海洋安全保障を確保することができます。日本は、イノベーションを通じて海上安全を推進するため、研究開発に重点を置いています。研究開発センターへの投資は、先進的な海上技術と安全ソリューションの開発に重点を置いています。
海事教育と訓練は、日本が確立した海上安全のシステムにおいて非常に重要な役割を果たしています。これは、海上保安大学校や海事大学校など、熟練した海事専門家の育成に関連する包括的なプログラムを実施している機関において見られます。あらゆるレベルの資格認定と継続的な専門能力開発プログラムにより、海事関係者が高い能力と安全性を維持するための最も安全で最新の実務と技術に対応できるようになっています。その他の不可欠な部分は、日本における海上安全への取り組みに対する国民の認識と地域社会の関与です。海上安全と海洋環境の保護に関する情報キャンペーンを実施することで、国民に安全意識と責任感を植え付けることができます。また、海上の安全に地域社会が参加することで、規制に対する地域社会の支持が強まり、海洋環境の保護に対する責任の共有が促進され、最終的には海上の安全に対する総合的な取り組みにつながります。例えば、ゼネラル・アトミクス・アエロナバル・システムズ社は、海上自衛隊の中高度・長時間RPAS試験運用プロジェクトに採用されました。このプロジェクトではGA-ASIのMQ-9Bシーガーディアン®を活用し、適応性と人員削減能力をテストします。日本政府は、海上保安庁と海上自衛隊がそれぞれ運用するMQ-9Bのデータを共有します。
日本の海上安全システム市場は、海上における安全確保と効率化を両立させる重要な要素です。日本の海上安全システムの市場では、ソリューション部門がハードウェアとソフトウェアを組み合わせて、交通安全のための包括的なソリューションを提供しています。フルノのNAVpilotシリーズのようなアプリケーションを通じて、複数の高度なナビゲーションシステムが組み合わされ、GPS、レーダー、AISからのリアルタイム情報による状況認識と、最適化された航路計画が提供されます。適切な緊急対応手順や国際的な海上安全管理システムの遵守は、ABS Nautical Systemsが提供するような安全管理システムの運用実績がある企業でなければ保証できません。そのため、MarineTraffic社が提供するような船隊管理ソリューションは、多数の船舶をリアルタイムで監視することで、運航効率と安全性を高めることができます。例えば、日本郵船は最先端の船隊管理システムを使って船舶運航を管理しています。現在、サイバーセキュリティ・ソリューションに対するニーズが高まっており、そのようなニーズに対応する企業には、海事システムを脅威から守る強力なセキュリティ対策を提供するフォーティネットなどがあります。フォーティネットは、海事システムを脅威から保護する強力なセキュリティ対策を提供しています。これらは、日本の海事活動に関連する安全全体を見据えるために統合された総合的な安全システムであり、業務の有効性と安全性を近代化します。このサービスは、日本の海上安全システム市場において、安全システムの導入、保守、運用を行う上で極めて重要です。設置および統合サービスは、ハードウェアおよびソフトウェア部品を適切に設置し、既存の海上業務と円滑に統合するようなものです。例えば、三井E&Sは据付・インテグレーションサービスを提供しています。定期的な点検・修理・更新などの保守・サポート活動は、継続的な機能・信頼性の維持とシステム障害の未然防止に貢献します。例えば、JRCSは、海上安全機器のメンテナンスサービスを提供しています。このようなサービスは、高度な安全システムの実運用や管理に向けた海上保安要員の訓練に影響を与えます。また、海上保安庁のように総合的な訓練を提供する機関もあります。コンサルタント・サービスは、海事事業者があらゆる要件に適した安全ソリューションを設計し、実施するのを支援するもので、ClassNKの日本海事協会のような企業がコンサルタント業務の専門知識を提供しています。遠隔監視・診断サービスは、船舶の安全関連システムのリアルタイム監視と故障診断を提案することで、この分野で脚光を浴びています。
日本は、世界の海運業界の主要な一員であり、海事分野における技術革新への関与の証である、高度に発達した海運保安システムを有しています。同じ理由から、日本における海運保安の重要な要素の一つは、海上保安庁の庇護の下にあります。日本は、非常に包括的で技術的に進んだ海上安全の枠組みを有しており、世界で最も多忙な海域の1つにおける要件に対応することができます。日本では、船舶の保安報告がやや厳格であり、到着前情報の形でかなりの詳細が海上交通情報システムを通じて船舶から提出される必要があります。長い海岸線と交通量の多いシーレーンにより、全国的な船舶自動識別システム(AIS)ネットワークがすでに構築されています。これは、瀬戸内海や東京湾のような混雑した海域で必要なものです。海上保安庁は、沿岸無線局や海難救助調整センターの統合運用を通じて、グローバルな海上遭難安全システムを運用しています。日本は、長距離識別追跡(LRIT)システムに積極的に参加しています。これまでに、日本国旗を掲げた船舶を世界規模で追跡する国家LRITデータセンターを設立しています。横浜や神戸のような主要な港に加え、このような洗練されたVTSシステムとその最新鋭のセンターの開発に実際に資金を費やしてきました。日本は、おそらく世界で最も先進的な船舶管理システムの1つを持っており、衛星技術の採用を通じて漁船団を監視しています。日本は、人工知能を利用した港湾インフラの予知保全や、船舶の自律運航の実現など、新たな海洋安全技術の開発と導入におけるパイオニアです。日本の海洋安全装置産業は、世界で最も進んだ産業のひとつです。フルノや日本無線といった企業は、最先端の航行・通信システムのほとんどを世界市場に輸出しています。津波に対する早期警報システムや海洋状況のリアルタイム監視の分野でも、日本は先陣を切り続けています。日本は、1910年に締結された「船舶の衝突に関する一定の規則の統一に関する条約」の締約国であり、締結国間の衝突および日本籍船同士の衝突については条約を締結していますが、日本または非締結国間の衝突については条約を締結していません。最後に、2018年に改正された商法について言及する必要があると思われます。
日本の海上安全システムの複雑なサービスとソリューションのネットワークは、政府・防衛、海洋・建設、石油・ガス、海運・運輸の各エンドユーザーの固有のニーズに対応しています。政府・防衛分野では、海上保安庁や国土交通省が関与する海上の安全規制や取締りなどの優先的なサービスを提供しています。海上保安庁と海上自衛隊は、海上の安全保障と防衛活動を保証します。N-VTSは、海上における海域認識、捜索救助、緊急対処の連携などを支援する最先端のシステム。特に、灯台やブイのような航行援助施設やインフラの建設と維持は、このシステムの維持に不可欠です。日本の海上安全システムは、国土交通省と日本海事協会(ClassNK)を通じて、海洋・建設分野のあらゆる海上工事プロジェクト、掘削プラットフォーム、エンジニアリング船の安全検査と認証を提供します。これにより、建設や浚渫における環境・安全法令の遵守が保証されます。同時に、リアルタイムな海上安全情報や建設船に関する航行支援も提供します。また、事故や環境事故が発生した場合の緊急対応や危機管理計画も保証します。国土交通省と日本海事検定協会が管轄する石油・ガス分野では、海上石油・ガスプラットフォーム、掘削リグ、支援船の安全検査・認証サービスを提供しています。日本の海上安全システムは、探査、生産、輸送活動が環境と安全に関する法律と規制に準拠していることを確認します。タンカー運航の海上保安支援には、船舶間輸送やその他の港湾業務が含まれます。
海運業では、貨物船、ばら積み貨物船、旅客船を含む商船の海上安全を確立し、実施しなければなりません。この分野では、国土交通省と船級協会が非常に重要な役割を果たしています。日本の海上安全システムは、船舶交通の管理と監視に自動識別システムや長距離識別追跡システムなどの高度な技術を適用しています。海事安全庁は、船員や海運業界関係者の海上安全教育や資格認定に携わる一方、一般的な捜索救助や緊急時対応は、商船運航への航行支援によって保証されています。運輸安全委員会(Japan Transport Safety Board) 航空機、鉄道、海事、重大事故の調査を行う国土交通省の独立機関。国土交通大臣に対し、調査結果に基づき必要な措置を講ずるよう要請し、事故の防止と被害の軽減に努めることを目的としています。また、海難事故や海難事故の原因究明を行うため、報告徴収、立入検査、関係者への質問、出頭要請などの権限を有しています。
本報告書の対象
– 歴史的な年 2018
– 基準年 2023
– 推定年 2024
– 予測年 2029
本レポートの対象分野
– 海上安全システム市場の展望とその価値とセグメント別予測
– 様々な推進要因と課題
– 進行中のトレンドと開発
– 企業プロフィール
– 戦略的提言
コンポーネント別
– ソリューション
– サービス別
セキュリティ種類別
– 港湾・重要インフラセキュリティ
– 沿岸警備
– 船舶セキュリティ
– 乗組員セキュリティ
– 貨物とコンテナの安全性
– 船舶システムと装置(SSE)の安全性
– その他のセキュリティ種類別
システム別
– 船舶保安通報システム
– 自動識別システム(AIS)
– 世界海上遭難安全システム(GMDSS)
– 長距離追跡識別(LRIT)システム
– 船舶監視・管理システム
エンドユーザー別
– 政府・防衛
– 海洋・建設
– 石油・ガス
– 船舶・輸送
– アプリケーション別
– 紛失防止・検知
– セキュリティ・安全管理
– 監視・追跡
– 捜索・救助
– その他
レポートのアプローチ
本レポートは一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されています。まず二次調査は、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために使用されます。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源で構成されています。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを実施し、市場のディーラーやディストリビューターとの取引コールを実施することによって行われました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始しました。一次データが得られれば、二次ソースから得た詳細の検証を開始することができます。
対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、海上安全システム業界関連組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を調整する際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションのほか、この業界に関する競合知識を高めることもできます。
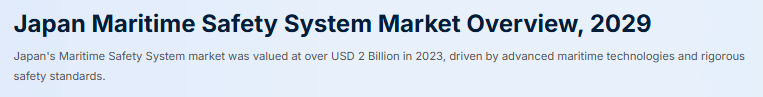
目次
- 1. 要旨
- 2. 市場構造
- 2.1. 市場考察
- 2.2. 前提条件
- 2.3. 制限事項
- 2.4. 略語
- 2.5. 情報源
- 2.6. 定義
- 2.7. 地理
- 3. 調査方法
- 3.1. 二次調査
- 3.2. 一次データ収集
- 3.3. 市場形成と検証
- 3.4. 報告書作成、品質チェック、納品
- 4. 日本のマクロ経済指標
- 5. 市場ダイナミクス
- 5.1. 市場促進要因と機会
- 5.2. 市場の阻害要因と課題
- 5.3. 市場動向
- 5.3.1. XXXX
- 5.3.2. XXXX
- 5.3.3. XXXX
- 5.3.4. XXXX
- 5.3.5. XXXX
- 5.4. コビッド19効果
- 5.5. サプライチェーン分析
- 5.6. 政策と規制の枠組み
- 5.7. 業界専門家の見解
- 6. 日本の海上安全システム市場の概要
- 6.1. 市場規模(金額ベース
- 6.2. 市場規模および予測、コンポーネント別
- 6.3. 市場規模・予測:システム別
- 6.4. 市場規模・予測:エンドユーザー別
- 6.5. 市場規模・予測:地域別
- 7. 日本の海上安全システム市場セグメント
- 7.1. 日本の海上安全システム市場:コンポーネント別
- 7.1.1. 日本の海上安全システム市場規模、ソリューション別、2018年~2029年
- 7.1.2. 日本の海上安全システムの市場規模、サービス別、2018年~2029年
- 7.2. 日本の海上安全システム市場:システム別
- 7.2.1. 日本の海上安全システムの市場規模:船舶安全報告システム別、2018年~2029年
- 7.2.2. 日本の海上安全システム市場規模:自動識別システム別、2018年〜2029年
- 7.2.3. 日本海上安全システムの市場規模:世界海上遭難安全システム別、2018年~2029年
- 7.2.4. 日本の海上安全システムの市場規模:長距離追跡・識別システム別、2018年~2029年
- 7.2.5. 日本の海上安全システムの市場規模:船舶監視・管理システム別、2018年~2029年
- 7.3. 日本の海上安全システム市場:エンドユーザー別
- 7.3.1. 日本の海上安全システムの市場規模:政府・防衛別、2018年〜2029年
- 7.3.2. 日本の海上安全システムの市場規模:海洋・建設別、2018年~2029年
- 7.3.3. 日本の海上安全システムの市場規模:石油・ガス別、2018年~2029年
- 7.4. 日本の海上安全システム市場規模:地域別
- 7.4.1. 日本の海上安全システムの市場規模:北部別、2018年〜2029年
- 7.4.2. 日本の海上安全システムの市場規模:東部別、2018年〜2029年
- 7.4.3. 日本の海上安全システムの市場規模:西日本別、2018年~2029年
- 7.4.4. 日本の海上安全システムの市場規模:南別、2018年~2029年
- 8. 日本の海上安全システムの市場機会評価
- 8.1. コンポーネント別、2024〜2029年
- 8.2. システム別、2024~2029年
- 8.3. エンドユーザー別、2024~2029年
- 8.4. 地域別、2024~2029年
- 9. 競争環境
- 9.1. ポーターの5つの力
- 9.2. 企業プロフィール
- 9.2.1. 企業1
- 9.2.1.1. 会社概要
- 9.2.1.2. 会社概要
- 9.2.1.3. 財務ハイライト
- 9.2.1.4. 地理的洞察
- 9.2.1.5. 事業セグメントと業績
- 9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
- 9.2.1.7. 主要役員
- 9.2.1.8. 戦略的な動きと展開
- 9.2.2. 企業2
- 9.2.3. 企業3
- 9.2.4. 4社目
- 9.2.5. 5社目
- 10. 戦略的提言
- 11. 免責事項

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
