日本の重要インフラ保護市場規模(~2029年)

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
日本市場の主な原動力は、国家の福利における重要インフラの重要性に対する認識の高まりです。これに伴い、サイバー脅威の頻度と巧妙さが増していることが、市場の成長に大きく寄与しています。重要インフラがデジタルシステムを通じてますます接続されるようになるにつれて、サイバー攻撃に対する脆弱性が増大し、潜在的な混乱から保護し、重要な業務の完全性を確保するための強固な保護対策が必要になっています。また、スマートシティの台頭やモノのインターネット(IoT)技術の重要インフラへの統合により、保護メカニズムの強化が求められています。スマートシティにおけるさまざまなシステムの相互接続は攻撃対象領域を拡大するため、CIPソリューションは、公共の安全、交通、エネルギー・グリッドを危険にさらす可能性のあるサイバー脅威を検出し、緩和するために極めて重要です。さらに、自然災害の増加や気候変動の影響により、回復力と適応力を備えた重要インフラの必要性が高まっています。物理的なセキュリティ対策や災害復旧戦略を含むCIPソリューションは、自然災害による潜在的な被害を最小限に抑え、重要なサービスを迅速に復旧させるために不可欠です。このため、市場には明るい展望が広がっています。さらに、厳しい規制の枠組みやコンプライアンス要件がCIP市場の成長に寄与しています。政府は、重要インフラを保護するための強固なセキュリティ対策を義務付ける厳しい規制を課しています。このような規制環境は、コンプライアンス基準を満たすためのCIPソリューションへの投資を促し、市場の拡大をさらに促進します。インフラの寸断が経済に与える影響に対する意識の高まりが、CIPソリューションの需要を促進しています。企業や政府は、重要なサービスの途絶によって発生する財務上および業務上の損失が大きいことを認識しており、包括的な保護対策への投資を動機づけています。
Bonafide Research社の調査レポート「日本の重要インフラ保護市場の展望、2029年」によると、日本の重要インフラ保護市場は2024年から29年までに1億米ドル以上に拡大すると予測されています。日本では、政府と政府以外のすべての人々との間のコミュニケーションの橋渡し役として機能する通知責任のメカニズムのほかに、各業界に情報交換と協議のためのチャネルを提供するために、業界間で情報共有と通知のメカニズムが確立されています。日本では2001年にテレコム情報共有分析センター(Telecom-ISAC Japan)を設立。テレコム・アイザック・ジャパンは、コンピュータ侵入インシデントのリアルタイム検査や情報収集・分析に加え、Transact-SQL問題に関連する多くの提案を電子政府に提案しています。Telecom-ISACを立ち上げた理由は、コンピュータ侵入インシデントを瞬時に検知し、その情報を瞬時に収集・分析し、他の通信事業者と情報交換を行い、適切な対応策を提示することで、社会経済に関わる重要なインフラである通信のセキュリティを確保するという目的を達成するためです。イノベーションを推進し、CIP戦略の効果を高めるためには、官民の協力が不可欠です。国際企業とのパートナーシップは、知識の移転や先進技術へのアクセスを促進し、地元企業がニーズに合ったソリューションを開発することを可能にします。さまざまな分野でデジタルトランスフォーメーションが加速する中、日本は重要インフラを標的としたサイバー脅威の増大に直面しています。注目された事件により、エネルギー、交通、医療などの重要サービスを守るための強固なサイバーセキュリティ対策の必要性が浮き彫りになっています。
日本の重要インフラ保護市場で最も大きなシェアを占めているのは、物理的セキュリティ&セーフティ分野です。これは、日本における物理的脅威、自然災害、テロ活動から、オープンスペース、重要サービス、重要資産を保護する必要性が背景にあります。この背景には、従来の物理的セキュリティ市場の成熟度、非常に厳格な規制の枠組み、監視、入退室管理、境界セキュリティに対するAIやIoTなどの新技術の早期導入など、多くの要因が考えられます。人口密度が高いこと、自然災害が頻発していること、オリンピックのような大規模なイベントを開催する必要があることも、効果的で厳重な物理的セキュリティの枠組みに関する導入の緊急性を下支えしています。同国は、公共の安全と緊急対応能力を向上させるため、物理的セキュリティ要素を統合したスマートシティ・ソリューションの展開に非常に積極的です。サイバーセキュリティ分野は、重要インフラのデジタル化の進展とサイバー脅威の頻度と複雑性の高まりに後押しされ、急成長を遂げています。日本がインダストリー4.0を導入し、デジタルトランスフォーメーションを推進する中で、重要インフラをサイバー攻撃から守る必要性が高まっています。日本政府は、サイバーセキュリティを向上させるための政策やガイドラインの策定に常に真剣に取り組んできました。その中には、サイバーセキュリティ戦略や、NISC(National Center of Incident Readiness and Strategy for Cybersecurity)の開発などがあります。また、より高度で新しいサイバーセキュリティ技術を生み出すための研究開発や、脅威インテリジェンスとベストプラクティスの共有という点で、官民間のパートナーシップの促進にも取り組んでいます。
現在、日本の重要インフラ保護市場では、エネルギー・電力分野がリードしています。これは、日本がエネルギーの輸入に大きく依存し、エネルギー安全保障の発展に戦略的な重点を置いているためと考えられます。世界最大の液化天然ガス輸入国であり、世界第3位の石油純輸入国である日本は、継続的な供給を確保し、脆弱性を軽減するため、エネルギーインフラの保護に細心の注意を払ってきました。この分野での強固な安全対策が必要不可欠であることをより明確にしているのは、再生可能エネルギーへの転換と発電の分散化です。2011年の福島第一原子力発電所の事故は、エネルギー・インフラ保護の重要性を改めて浮き彫りにし、この分野に莫大な投資が行われました。一方、BFSIセクターは急速な発展を遂げています。これは、金融サービスの急速なデジタル化によって、脆弱性が強化され、脅威の空間が広がったためと考えられます。つまり、キャッシュレス社会への移行に伴い、デジタル金融インフラを保護する必要性が高まるということです。例えば、大阪で開催が予定されている次回の万国博覧会では、安全で効率的な金融サービスへの需要が高まり、この分野の継続的な成長に拍車がかかるでしょう。もう一つの重要な分野は、IT・通信分野です。IT・通信分野は、他の多くの分野のインフラのバックボーンとして機能しています。この意味で、IT・通信分野を保護するということは、通信ネットワークが中断されることなく、安全で、利用可能であることを保証し、データが無傷で、アクセス可能であることを保証することを意味します。政府・防衛分野は、国家安全保障上の利益と公共サービスに重点を置く、もうひとつの重要な分野です。輸送・ロジスティクス分野は、モノや人のスムーズな流れに関連する分野であり、ここでのセキュリティは混乱を許さず、業務の安全を提供する役割を果たします。石油・ガス部門は、インフラとセキュリティのニーズが混在しがちな、より広範な「エネルギー・電力」部門と一緒に扱われることが多いものの、重要な部門です。
日本では、ソリューション部門がこの市場をリードしています。ソリューション分野は、リスクの効率的な軽減、脅威の特定、あらゆる種類のインシデントへのセキュリティ対応に焦点を当てた高度な技術やシステムを幅広く網羅しています。そのため、監視システム、入退室管理技術、侵入検知システム、サイバーセキュリティなど、高度なセキュリティ・ハードウェアおよびソフトウェアに対する高い需要が、ソリューション分野のシェアを大きく伸ばしています。強い技術力とイノベーションの視点を持つ日本は、変化する脅威から重要インフラを守るため、官民両部門で大規模な投資を行い、こうしたソリューションの採用を推進してきました。サービス分野でのシェア拡大と高成長は、セキュリティ課題の複雑化と、絶え間なく拡大するセキュリティシステムの処理と保守における高度な専門知識の必要性の高まりによるものです。専門的なセキュリティ・サービスは、マネージド・セキュリティ・サービス、インシデント対応、セキュリティ・コンサルティング、トレーニングのような高度なサービスを採用する重要インフラの相互接続とデジタル化の増加によって引き起こされるサイバー脅威のリスクの増大に伴い、需要が増加しています。セキュリティ・サービスを増加させているもう1つの課題は、規制やコンプライアンスの厳しい要求に対応するサービスの必要性です。また、セキュリティ機能を専門プロバイダーにアウトソーシングする傾向も、この分野をさらに後押ししています。これは、実施組織がコアコンピタンスに集中できるよう、セキュリティ機能を強化したアウトソーシングが登場している現在、実質的に実現されています。
本レポートの考察
– 歴史的な年 2018
– 基準年 2023
– 推定年 2024
– 予測年 2029
本レポートの対象分野
– 重要インフラ保護市場の展望とその価値とセグメント別予測
– さまざまな推進要因と課題
– 進行中のトレンドと開発
– 企業プロフィール
– 戦略的提言
セキュリティ種類別
– 物理的セキュリティと安全性
– サイバーセキュリティ
分野別
– エネルギー・電力
– BFSI
– IT・電気通信
– 政府・防衛
– 運輸・物流
– 石油・ガス
– その他の業種
サービス別
– ソリューション
– サービス
レポートのアプローチ
本レポートは一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されています。当初は、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために二次調査を使用しました。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源で構成されています。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを実施し、市場のディーラーやディストリビューターとの取引コールを実施することによって行われました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始しました。一次データが得られれば、二次ソースから得た詳細の検証を開始することができます。
対象読者
この調査レポートは、重要インフラ保護(Critical Infrastructure Protection)産業に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の関係者が、市場中心の戦略を立てる際にお役立ていただけます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、この業界に関する競合知識を高めることもできます。
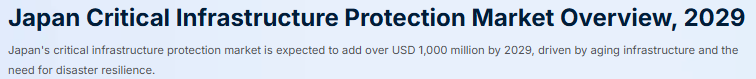
目次
1. 要旨
2. 市場構造
2.1. 市場考察
2.2. 前提条件
2.3. 制限事項
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3. 市場形成と検証
3.4. 報告書作成、品質チェック、納品
4. 日本のマクロ経済指標
5. 市場ダイナミクス
5.1. 市場促進要因と機会
5.2. 市場の阻害要因と課題
5.3. 市場動向
5.3.1. XXXX
5.3.2. XXXX
5.3.3. XXXX
5.3.4. XXXX
5.3.5. XXXX
5.4. コビッド19効果
5.5. サプライチェーン分析
5.6. 政策と規制の枠組み
5.7. 業界専門家の見解
6. 日本の重要インフラ保護市場の概要
6.1. 市場規模(金額ベース
6.2. 市場規模および予測、セキュリティ種類別
6.3. 市場規模・予測:業種別
6.4. 市場規模・予測:業種別
6.5. 市場規模・予測:地域別
7. 日本の重要インフラ保護市場の細分化
7.1. 日本の重要インフラ保護市場:セキュリティ種類別
7.1.1. 日本の重要インフラ保護市場規模:物理的セキュリティと安全性別、2018年~2029年
7.1.2. 日本の重要インフラ保護市場規模:サイバーセキュリティ別、2018年~2029年
7.2. 日本の重要インフラ保護市場規模:業種別
7.2.1. 日本の重要インフラ保護市場規模:エネルギー・電力別、2018年~2029年
7.2.2. 日本の重要インフラ保護市場規模:BFSI別、2018年~2029年
7.2.3. 日本の重要インフラ保護市場規模:IT・通信別、2018年~2029年
7.2.4. 日本の重要インフラ保護市場規模:政府・防衛別、2018年~2029年
7.2.5. 日本の重要インフラ保護市場規模:輸送・物流別、2018年~2029年
7.2.6. 日本の重要インフラ保護市場規模:石油・ガス別、2018年~2029年
7.2.7. 日本の重要インフラ保護市場規模:その他別、2018年~2029年
7.3. 日本の重要インフラ保護市場規模:業種別
7.3.1. 日本の重要インフラ保護市場規模:ソリューション別、2018年~2029年
7.3.2. 日本の重要インフラ保護市場規模:サービス別、2018年~2029年
7.4. 日本の重要インフラ保護市場規模:地域別
7.4.1. 日本の重要インフラ保護市場規模:北地域別、2018年~2029年
7.4.2. 日本の重要インフラ保護市場規模:東部別、2018年~2029年
7.4.3. 日本の重要インフラ保護市場規模:西日本別、2018年~2029年
7.4.4. 日本の重要インフラ保護市場規模:南地域別、2018年~2029年
8. 日本の重要インフラ保護市場の機会評価
8.1. セキュリティ種類別、2024年〜2029年
8.2. 分野別、2024~2029年
8.3. 業種別、2024~2029年
8.4. 地域別、2024~2029年
9. 競争環境
9.1. ポーターの5つの力
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 会社概要
9.2.1.2. 会社概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントと業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 主要役員
9.2.1.8. 戦略的な動きと展開
9.2.2. 企業2
9.2.3. 企業3
9.2.4. 4社目
9.2.5. 5社目
9.2.6. 6社
9.2.7. 7社
9.2.8. 8社
10. 戦略的提言
11. 免責事項

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
