日本のエネルギー貯蔵システム市場規模(~2029年)

| 本報告書では、日本のエネルギー貯蔵システム市場について詳細に分析し、現状や将来の展望を示しています。市場構造やダイナミクス、競争環境などの要素を考慮し、さまざまな側面から情報を提供しています。 まず、要旨として市場の全体像を把握し、市場の促進要因や阻害要因、そして市場動向を確認します。特に、コビッド19の影響やサプライチェーンの分析、政策と規制の枠組みについても触れています。これにより、エネルギー貯蔵システムの市場の現状を理解することができます。 次に、日本のエネルギー貯蔵システム市場の概要について、市场規模を金額ベースで示し、種類別や用途別の予測も行っています。具体的には、蓄電池、揚水発電、熱エネルギー貯蔵、フライホイール式エネルギー貯蔵など、さまざまなタイプの市場規模を分析しています。また、家庭用や商業・産業用の用途別の市場規模も示しています。 市場機会の評価においては、2024年から2029年までの期間を対象に、種類別およびアプリケーション別の機会を検討しています。この分析により、投資家や企業にとっての潜在的なビジネスチャンスが明確になります。 競争環境に関しては、ポーターの5つの力を用いて市場競争の構造を評価し、主要企業のプロフィールを詳述しています。各企業の財務状況や地理的な洞察、製品ポートフォリオ、戦略的な動きについても情報を提供し、市場における競争の激しさを理解するための基盤を築いています。 最後に、戦略的提言として、今後の市場における成功のための戦略や方向性を示唆しています。これにより、関係者は市場動向に基づいた意思決定を行いやすくなるでしょう。 本報告書は、エネルギー貯蔵システム市場に関心を持つすべての関係者にとって、重要な情報源となることを目指しています。 |
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
日本のエネルギー貯蔵システム(ESS)市場は、エネルギー分野における比類なき機会を生み出す様々な要因によって、著しい変化を遂げています。この変化の中核にあるのは、太陽光発電やその他の再生可能エネルギーの導入拡大です。日本の太陽光発電設備の多くは家庭用の屋根に設置されており、ピーク時の太陽光エネルギー利用を最適化し、日照時間の変動を管理するというユニークな課題を生み出しています。そこで注目されているのが、日本のESS市場です。近年、ソーラー・ストレージ・システムの設置が大幅に増加しており、日本は住宅用ESSの普及においてアジアをリードする存在となっています。日本の野心は、家庭用太陽光発電と蓄電にとどまりません。温室効果ガスの排出削減に取り組む日本では、風力発電や太陽光発電のような再生可能エネルギーの割合の増加に対応するため、堅牢な送電網インフラが必要です。大規模蓄電池システムは、このような状況において極めて重要な役割を果たします。ユーティリティ・スケールの蓄電プロジェクトにおける日本企業と海外企業との協力関係は、日本がこの技術の進歩に専心していることを示すものです。日本の規制環境もまた、ESS市場に独自の利点をもたらしています。系統運用者にESSへのネットワークアクセスを義務付ける明確なガイドラインは、市場参加者にとって有益なエコシステムを形成しています。低金利ローンや電池システムに対する補助金といった金融面の優遇措置は、業界の成長に有利な条件を作り出しています。日本のESS市場は、家庭用分野で著しい成長を遂げ、目覚ましい業績を上げています。2024年末までには、リチウムイオン電池のコスト低下に牽引され、日本の数百万世帯がエネルギー貯蔵システムを導入すると予測されています。日本のESS市場の新たなトレンドは、再生リチウムイオン電池への注目です。環境意識のリーダーとして、日本は電気自動車(EV)用電池のセカンドライフ・アプリケーションを積極的に模索しています。このアプローチは、特に大規模プロジェクトにおいて、定置型蓄電のニーズに持続可能でコスト効率の高いソリューションを提供します。リサイクル・バッテリーを取り入れることで、企業は環境面での信用を高めながら、循環経済を推進する政府のイニシアティブに沿うことができます。このような持続可能性の重視により、日本企業は世界のESS産業の最前線に位置しています。
Bonafide Research社の調査レポート「日本のエネルギー貯蔵システム市場の概要、2029年」によると、日本のエネルギー貯蔵システム市場は2024年時点で約130億米ドルと評価されています。日本のエネルギー貯蔵システム(ESS)市場は、その景観を形成するトレンド、促進要因、課題のユニークな融合によって特徴付けられます。主な推進要因は、2050年までにカーボンニュートラルを達成するという日本の野心的な目標であり、これには再生可能エネルギー源への大幅なシフトと、風力発電や太陽光発電の変動性を管理するための大規模なESS統合が必要です。このようなエネルギー情勢の変化は、グリッド規模の蓄電池システムに対する需要の増加につながり、その中でもリチウムイオン(Li-ion)電池は応答時間が速く、拡張性に優れているため、人気の高い選択肢となっています。日本政府は、再生可能エネルギープロジェクトに対する補助金やスマートグリッドの開発を促進するイニシアチブなど、有利な政策を通じてこの移行を支援しています。日本における電気自動車(EV)市場の急成長は、EV充電インフラとマイクログリッド・アプリケーションをサポートする分散型蓄電池ソリューションのニーズを促進しています。技術の進歩は、日本のESS市場におけるもう一つの重要なトレンドです。電池性能の向上、コスト削減、そして引退したEV用電池の革新的なセカンドライフ・アプリケーションの探求への取り組みが、市場の将来を形成しています。日本はまた、デジタル化とスマートグリッド開発に重点を置く国の方針に沿って、遠隔監視・分析機能を備えたクラウドベースのESS管理システム導入の最前線にいます。日本のESS市場はいくつかの課題に直面しています。厳しい安全規制とバッテリー火災の懸念により、堅牢なバッテリー管理システムの導入と安全基準の厳格な遵守が必要。シームレスなグリッド統合の確保と、蓄電されたエネルギーを取引するための効率的な市場メカニズムの開発は、依然として重要な課題です。さらに、日本では大規模な蓄電池を設置できる土地が限られているため、揚水発電や圧縮空気蓄電(CAES)のような、適切な地層を利用した代替蓄電ソリューションの検討が必要です。
日本のエネルギー貯蔵システム市場は、種類別に電池、揚水発電(PSH)、熱エネルギー貯蔵(TES)、フライホイール・エネルギー貯蔵(FES)、その他のタイプに分類することができます。各セグメントは、ユニークな利点を提供し、特定の要件に対応し、国のエネルギー貯蔵の状況で重要な役割を果たしています。電池は、日本のエネルギー貯蔵市場において支配的なセグメントであり、リチウムイオン電池が様々な用途で主要な選択肢となっています。再生可能エネルギー源、電気自動車、スマートグリッドの普及が、電池セグメントの成長に大きく貢献しています。電池の性能、寿命、費用対効果の向上を目指した継続的な研究開発が、この分野の拡大を後押ししています。揚水発電(PSH)も日本の主要なエネルギー貯蔵技術です。PSHは大規模なエネルギー貯蔵能力を提供し、ピーク時の送電網のバランスをとるのに役立ちます。環境問題や地理的な制約にもかかわらず、PSHは日本のエネルギー貯蔵戦略において重要な要素であり続けています。熱エネルギー貯蔵(TES)は、特に冷暖房システムなどの用途で、日本で普及しつつあります。TESシステムは、熱や冷熱の形でエネルギーを貯蔵し、必要に応じて放出することで、様々な産業・商業プロセスの効率と費用対効果を改善します。集光型太陽光発電のような再生可能エネルギー源とTESの統合は、将来的に大きな可能性を秘めています。フライホイールエネルギー貯蔵(FES)は、日本のエネルギー貯蔵市場で成長している分野です。FESシステムは、ローターを高速に加速することで運動エネルギーの形でエネルギーを貯蔵し、必要なときに電気として放出します。この技術は、高速応答時間、高効率、長サイクル寿命を実現し、周波数調整、系統安定化、その他のアンシラリーサービスに適しています。種類別」セグメントには、圧縮空気エネルギー貯蔵(CAES)、スーパーキャパシタ、水素貯蔵などの新興・ニッチエネルギー貯蔵技術が含まれます。これらの技術は特定のエネルギー貯蔵要件に対応し、独自の利点を提供するため、日本のエネルギー貯蔵市場の多様化に寄与しています。
家庭用分野は、屋根上太陽光発電システムの導入増加、政府による奨励措置、自然災害時のバックアップ電源のニーズの高まりなどを背景に、日本で大きな成長を遂げています。住宅所有者は、日中に発電した太陽光エネルギーの余剰分を蓄電し、ピーク時や系統電力が利用できないときに利用するために、蓄電システムを利用するようになってきています。太陽光発電と蓄電池の組み合わせにより、一般家庭は送電網への依存度を減らし、電気料金を下げ、日本の再生可能エネルギー目標に貢献することができます。商業・産業分野は、エネルギー管理の改善、運用コストの削減、持続可能性の向上を目指す企業が日本のエネルギー貯蔵市場をリードしています。エネルギー貯蔵システムにより、商業・産業施設は再生可能エネルギー源から発電された電気や、電気料金が安いオフピーク時に発電された電気を貯蔵することができます。この蓄電されたエネルギーを需要ピーク時に利用することで、エネルギーコストを削減し、デマンドチャージを回避し、安定した電力供給を確保することができます。さらに、エネルギー貯蔵システムは停電時にバックアップ電力を供給し、事業の継続性を確保するとともに、電力途絶による経済的な影響を最小限に抑えます。電気自動車(EV)の普及が進み、EV充電インフラが整備されていることも、商業・産業分野の成長に寄与しています。エネルギー貯蔵システムを充電ステーションと統合することで、負荷を管理してエネルギー使用を最適化し、送電網への負担を減らして充電コストを削減することができます。その他」のアプリケーション・セグメントには、ユーティリティ規模のエネルギー貯蔵プロジェクトとアンシラリー・サービスが含まれます。ユーティリティ規模の蓄電システムは、系統運用者が需要と供給のバランスを取り、再生可能エネルギー源を統合し、系統の安定性を維持するのに役立ちます。このような大規模プロジェクトでは、揚水発電(PSH)、リチウムイオン電池、その他の高度な蓄電ソリューションなどの技術が採用されることがよくあります。周波数調整、電圧制御、ブラックスタート機能などのアンシラリーサービスは、信頼性が高く効率的な送電網を維持するために不可欠であり、この分野におけるエネルギー貯蔵システムの需要をさらに促進しています。
日本のエネルギー貯蔵市場は、日本のエネルギー状況を再構築し、持続可能な電源の採用を推進する上で極めて重要な役割を果たしています。クリーンで再生可能なエネルギーへの需要が拡大し続ける中、エネルギー貯蔵システムは、風力発電や太陽光発電などの変動する再生可能エネルギー源をシームレスに統合するために不可欠なものとなっています。日本におけるエネルギー貯蔵市場の拡大は、将来的な持続可能な電源の導入に大きく影響します。再生可能エネルギーによって発電された余剰エネルギーを貯蔵するソリューションを提供することで、エネルギー貯蔵システムは断続性の問題に効果的に対処し、安定した一貫した電力供給を実現します。ひいては、日本のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの全体的な割合を高め、日本の野心的な再生可能エネルギー目標に貢献することができます。蓄電システムの普及は、日本のエネルギーインフラ全体にも好影響を与えます。より多くの再生可能エネルギーを送電網に統合できるようにすることで、エネルギー貯蔵システムは、従来の化石燃料を使用した発電への日本の依存度を下げるのに役立ちます。このシフトは、温室効果ガスの大幅な削減につながり、低炭素社会の実現という日本の目標に貢献します。 蓄電システムの導入は、日本のエネルギーインフラ全体の回復力を高めることができます。送電網の停止やその他の障害時にバックアップ電力を供給することで、蓄電システムは消費者により信頼性の高い安全なエネルギー供給を保証することができます。
本レポートの考察
– 歴史的な年 2018
– 基準年 2023
– 推定年 2024
– 予測年 2029
本レポートの対象分野
– 救急医療機器市場の展望とその価値とセグメント別予測
– 様々な促進要因と課題
– 進行中のトレンドと開発
– 企業プロフィール
– 戦略的提言
種類別
– 救急蘇生機器
– 診断用医療機器
– 個人用保護具
– 患者対応機器
– その他の機器
種類別
– 外傷
– 心臓ケア
– 呼吸器ケア
– 腫瘍学
– その他
エンドユーザー別
– 病院
– 専門クリニック
– 外来手術センター
– その他
レポートのアプローチ
本レポートは一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されています。まず二次調査では、市場の把握と参入企業のリストアップを行いました。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源で構成されています。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを実施し、市場のディーラーやディストリビューターとの取引コールを実施することによって行われました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始しました。一次データを入手したら、二次ソースから得た詳細の検証を開始します。
対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、救急医療機器業界に関連する組織、政府機関、その他の関係者が市場中心の戦略を調整する際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。
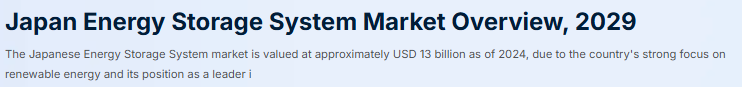
目次
1. 要旨
2. 市場構造
2.1. 市場考察
2.2. 前提条件
2.3. 制限事項
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3. 市場形成と検証
3.4. 報告書作成、品質チェック、納品
4. 日本のマクロ経済指標
5. 市場ダイナミクス
5.1. 市場促進要因と機会
5.2. 市場の阻害要因と課題
5.3. 市場動向
5.3.1. XXXX
5.3.2. XXXX
5.3.3. XXXX
5.3.4. XXXX
5.3.5. XXXX
5.4. コビッド19効果
5.5. サプライチェーン分析
5.6. 政策と規制の枠組み
5.7. 業界専門家の見解
6. 日本のエネルギー貯蔵システム市場の概要
6.1. 市場規模(金額ベース
6.2. 市場規模・予測:種類別
6.3. 市場規模・予測:用途別
7. 日本の蓄電システム市場セグメント
7.1. 日本の蓄電システム市場:種類別
7.1.1. 日本の蓄電システム市場規模、電池別、2018年〜2029年
7.1.2. 日本のエネルギー貯蔵システム市場規模:揚水発電(PSH)別、2018年~2029年
7.1.3. 日本のエネルギー貯蔵システム市場規模:熱エネルギー貯蔵(TES)別、2018年~2029年
7.1.4. 日本のエネルギー貯蔵システム市場規模:フライホイール式エネルギー貯蔵(FES)別、2018年~2029年
7.1.5. 日本のエネルギー貯蔵システムの市場規模、種類別、2018年~2029年
7.2. 日本のエネルギー貯蔵システム市場:用途別
7.2.1. 日本の蓄電システム市場規模:家庭用別、2018年〜2029年
7.2.2. 日本の蓄電システム市場規模:商業・産業別、2018年~2029年
8. 日本のエネルギー貯蔵システム市場の機会評価
8.1. 種類別、2024〜2029年
8.2. アプリケーション別、2024~2029年
9. 競争環境
9.1. ポーターの5つの力
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 会社概要
9.2.1.2. 会社概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントと業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 主要役員
9.2.1.8. 戦略的な動きと展開
9.2.2. 企業2
9.2.3. 企業3
9.2.4. 4社目
9.2.5. 5社目
9.2.6. 6社
9.2.7. 7社
9.2.8. 8社
10. 戦略的提言
11. 免責事項

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
