日本の環境修復市場規模(~2029年)

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
環境修復に向けた日本のコミットメントは、さまざまな環境修復イニシアチブのための強力な研究開発によって裏付けられています。研究機関、大学、民間企業間の連携により、汚染の抑制、廃棄物の管理、(劣化した)生態系の回復に必要な技術の数々を生み出す機運が高まっています。これには、汚染された土壌や水を浄化するための新しい高性能材料の開発、環境汚染物質をモニタリングするためのセンサー開発の強化、さらには環境的に持続可能な管理のための実行可能な解決策を提供するバイオテクノロジーに基づくアプローチなどが含まれます。人工知能、機械学習、ビッグデータ解析の導入は、最適化された修復戦略のための予測モデリングや意思決定支援システムの導入により、日本の能力をさらに高めることに貢献します。生態系の再生は、生物多様性と生態系の回復力を促進するため、日本の環境政策の第二の柱です。植林、湿地や海岸の再生、都市のグリーンインフラの構築など、さまざまなプログラムが実施されています。これらのプロジェクトは、単に環境への悪影響を減らすだけでなく、炭素隔離、洪水防止、野生生物の生息地の提供など、非常に価値のある生態系サービスを提供します。これは、環境保全と社会経済的便益の達成をバランスよく両立させるために、政府機関、NGO、地域コミュニティ、企業パートナーが協力することで保証されます。国際的には、日本は持続可能な開発のための世界的な環境協力に非常に積極的です。日本は、さまざまな国際機関や政府との共同研究プログラム、能力開発イニシアティブ、技術移転協定を通じて、地球環境ガバナンスの実施を強化しています。UNEPのような取り組みへの加盟は、環境管理、災害リスク軽減、気候変動緩和のベストプラクティスを世界規模で推進するのに役立っています。特に福島第一原子力発電所事故の後、核汚染に関して日本が直面している他の国にはない課題があります。そのため、除染、放射性廃棄物の管理、環境放射線のモニタリングなど、浄化に向けた取り組みが行われています。例えば、エコサイクル株式会社は、有害化学物質で汚染された土壌や地下水の浄化プロセスに革命をもたらした「原位置浄化」を主要戦略とする包括的アプローチを開発しました。
Bonafide Research社の調査レポート「日本の環境修復市場の概要、2029年」によると、日本の環境修復市場は2024年から29年までに40億米ドル以上になると予測されています。日本は、1950年代から60年代にかけて、いわゆる水俣湾の水銀中毒事件のような環境汚染事件の記録を持っています。そのため日本政府は、さらなる環境破壊を防ぎ、公衆衛生を守るため、規制を厳しくしました。これを守らないものには、罰金や懲役などの厳しい罰則が科せられます。日本の環境修復産業を牽引している要因は、公衆衛生への懸念です。日本は人口密度の高い国であり、人々は環境汚染が起こりやすい工業用地やその他の場所の大半のすぐ近くに住んでいます。こうしたことから、環境汚染が公衆衛生にもたらす潜在的リスクに対する認識が高まり、公衆衛生を尊重し保護する浄化サービスに対する需要が高まっている。こうした要因に加えて、日本の浄化業界では持続可能な開発への関心が高まっています。例えば、ナノテクノロジーに基づくソリューションや微生物によるバイオレメディエーションといった新技術の適用への関与。雨水やその他の雨水が土壌に流出し、浸食の原因となる量を軽減するのに役立つ、透水性舗装や屋上緑化などのグリーン・インフラも増加しています。日本の環境修復分野に関連する例としては、地下水浄化のための太陽光発電ポンプがあります。汚染された土壌や瓦礫を建設資材として再利用したり、植物を利用して土壌や地下水から特定の汚染物質を除去するファイトレメディエーション技術の実用化が進んでいます。
日本は、多くのバイオレメディエーション技術を採用し、早くからその開発と応用をリードしてきました。汚染土壌の掘削と原位置処理は、現在でも一般的に行われています。認可施設による土壌の処理には、熱脱着、土壌洗浄、安定化、生物処理などがあります。塩素系溶剤やその他の地下水汚染物質のプルームを処理するために、ゼロ価の鉄やその他の反応剤を使用したPRBが多くのサイトで実施されています。エアスパージングと土壌蒸気抽出は、地下土壌や地下水中のVOCの原位置生分解を誘導するのに最適な最も一般的な方法の2つです。過マンガン酸塩、過硫酸塩、フェントン試薬などの酸化剤を使用した化学酸化は、最近人気が高まっています。このプロセスは多くの場合、土壌混合や注入法とともに行われます。重金属やダイオキシンによって汚染された低透水性土壌に対しては、電流を利用した動電学的浄化法のパイロットテストが日本で実施されています。ヤナギの木やイネ科の植物を用いたファイトレメディエーションは、日本における広範な研究の焦点であり、有機汚染物質や金属で汚染されたいくつかの場所の浄化に使用されています。バイオレメディエーションは、バイオオーグメンテーション、酵素/界面活性剤の添加、嫌気性生分解プロセスなどの技術を含め、日本の活発な研究プログラムで研究されています。日本の環境修復市場は、「汚染者負担」の原則が責任に関する法律に盛り込まれた強力な規制と監督によって大きく動かされています。
日本では、厳しい特別規制とその執行メカニズムに後押しされ、環境修復産業が発達しています。化学製品の生産、自動車製造工場などの製造業は、環境修復サービスの大きな消費者です。掘削、土壌洗浄、化学酸化、熱処理、安定化は、塩素系溶剤、重金属、石油炭化水素、その他多くの汚染物質に対処するための最も一般的な技術です。他国に比べ規模は小さいものの、日本には石油・ガス産業があり、様々な探査・生産・流通施設において土壌・地下水の浄化が必要とされています。エアスパージング、バイオベント、栄養塩添加などのバイオレメディエーション法が実施されています。建設と土地の再開発は、日本におけるもう一つの重要な浄化促進要因です。工業用地の再開発が進み、厳しい基準での浄化が義務付けられています。この種のブラウンフィールド・プロジェクトには、原位置および原位置処理トレインが適切に設計されています。日本の一部では、農業によって土壌や地下水が農薬で汚染されています。このため、研究者たちはファイトレメディエーション(植物による土壌浄化)のような治療法を研究しています。鉱業によって影響を受けた土地では、安定化処理や酸性鉱山排水処理を含む土壌浄化が必要です。日本の固形廃棄物処分場は封じ込めシステムで建設されていますが、古い処分場や不法投棄された処分場は、汚染が確認されれば、バイオレメディエーション、キャッピング、浸出液処理法を用いて浄化することができます。
日本では現在、公共用地が最も一般的な汚染浄化用地となっていますが、そのほとんどは、日本の急速な工業化時代に政府が運営していた工業施設跡地です。日本政府はこのようなサイトの浄化に取り組んでおり、過去数年間に行われた浄化に関しては、非常に素晴らしい実績があります。例えば、東京湾にある東京ガスの跡地は、コールタールやその他の化学物質でひどく汚染されていましたが、浄化のための大規模な努力の後、非常に人気のある公共の公園として生まれ変わりました。民間サイトも、日本で汚染土壌や地下水の浄化が進んでいる分野のひとつです。日本では人口が密集し、利用可能な土地が少ないため、汚染されたブラウンフィールドを商業用地や住宅用地として再開発しようという圧力が高まっています。そのため、民間企業による浄化サービスの需要が高まっています。例えば、横浜の元工業用地は重金属やその他の化学物質で汚染されていましたが、修復され、大規模に再開発されて複合商業施設になりました。
日本には、厳しい規制と長い工業化によってもたらされた汚染土壌の境界の中で、伝統的に操業してきた環境修復産業が非常に発達しています。主に、重金属、ダイオキシン、PCB、石油炭化水素を軽減するために主に適用されてきた掘削、土壌洗浄、熱脱着、安定化などの従来の技術を使用して、旧製造施設、ブラウンフィールド、石油処理事業、再開発物件の土壌の浄化に重点が置かれてきました。また、透水性の低い土壌マトリクスを処理するために、電気動力学、ファイトレメディエーション、酸化・還元プロセスなどの革新的な技術がパイロット規模で応用されています。日本で急拡大している新市場は、土壌浄化とは対照的に地下水浄化であり、これは引き続き最重要課題である。これは主に、塩素系溶剤プルーム、高濃度非水相液体、その他の難分解性汚染物質の浄化の結果です。汚染地下水の制御と処理に広く適用されるようになっている技術には、浸透性反応バリア、原位置化学酸化/還元、エアスパージング、バイオスパージング、強化バイオレメディエーション、ポンプアンドトリートシステムなどがあります。一方、1,4-ジオキサンやPFASのような従来とは異なる地下水質の新たな汚染物質を処理するため、新たな生物学的、化学的、熱的解決策が研究開発されています。
本レポートの考察
– 歴史的な年 2018
– 基準年 2023
– 推定年 2024
– 予測年 2029
本レポートの対象分野
– 環境修復市場の展望とその価値とセグメント別予測
– 様々な推進要因と課題
– 進行中のトレンドと開発
– 企業プロフィール
– 戦略的提言
技術別
– バイオレメディエーション
– 掘削
– 透過性反応バリア
– 空気温存
– 土壌洗浄
– 化学処理
– 電撃浄化
– その他
用途別
– 石油・ガス
– 製造、工業、化学生産/処理
– 自動車
– 建設・土地開発
– 農業
– 鉱業・林業
– 埋立地および廃棄物処理場
– その他
種類別
– 公共
– 民間
媒体別
– 土壌
– 地下水
レポートのアプローチ
本レポートは一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されています。まず二次調査は、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために使用しました。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源で構成されています。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを実施し、市場のディーラーやディストリビューターとの取引コールを実施することによって行われました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始しました。一次データが得られれば、二次ソースから得た詳細の検証を開始することができます。
対象読者
本レポートは、環境修復産業に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他の利害関係者が市場中心の戦略を調整する際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。
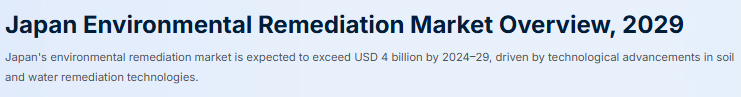
目次
- 1 エグゼクティブサマリー
- 2 市場構造
- 2.1 市場考察
- 2.2 前提
- 2.3 制限
- 2.4 略語
- 2.5 出典
- 2.6 定義
- 2.7 ジオグラフ
- 3 調査方法
- 3.1 二次調査
- 3.2 一次データ収集
- 3.3 市場形成と検証
- 3.4 報告書作成、品質チェック、納品
- 4 日本マクロ経済指標
- 5 市場動向
- 5.1 市場促進要因と機会
- 5.2 市場の阻害要因と課題
- 5.3 市場動向
- 5.3.1 XXX
- 5.3.2 XXX
- 5.3.3 XXX
- 5.3.4 XXX
- 5.3.5 XXX
- 5.4 コビッド19エフェック
- 5.5 サプライチェーン分析
- 5.6 政策と規制の枠組み
- 5.7 業界専門家の見解
- 6 日本の環境修復市場の概観
- 6.1 市場規模
- 6.2 市場規模および予測、技術別
- 6.3 市場規模・予測:アプリケーション別
- 6.4 市場規模・予測:サイトタイプ別
- 6.5 市場規模・予測:医療機関別
- 7 日本の環境修復市場のセグメンテーション
- 7.1 日本の環境修復市場、技術別
- 7.1.1 日本の環境修復市場規模、バイオレメディエーション別、2018年〜202年
- 7.1.2 日本の環境修復市場規模:掘削工法別、2018年〜202年
- 7.1.3 日本の環境修復市場規模:透水性反応バリア別、2018年〜202年
- 7.1.4 日本の環境修復市場規模:エアスパージング別、2018年〜202年
- 7.1.5 日本の環境修復市場規模:土壌洗浄別、2018年-202年
- 7.1.6 日本の環境修復市場規模:化学処理別、2018年〜202年
- 7.1.7 日本の環境修復市場規模:動電学的修復別 、2018年-202年
- 7.1.8 日本の環境修復市場規模:その他別、2018年-202年
- 7.2 日本の環境修復市場:用途別
- 7.2.1 日本の環境修復市場規模:石油・ガス別、2018年〜202年
- 7.2.2 日本の環境修復市場規模:製造業、工業、化学生産/処理別、2018年〜202年
- 7.2.3 日本の環境修復市場規模:自動車別、2018年〜202年
- 7.2.4 日本の環境修復市場規模:建設・土地開発別 2018-202
- 7.2.5 日本の環境修復市場規模:農業別 2018-202
- 7.2.6 日本の環境修復市場規模:鉱業・林業別 2018-202
- 7.2.7 日本の環境修復市場規模:埋立地・廃棄物処分場別、2018年〜202年
- 7.2.8 日本の環境修復市場規模:その他別、2018年〜202年
- 7.3 日本の環境修復市場:サイトタイプ別
- 7.3.1 日本の環境修復市場規模:公共施設別、2018年〜202年
- 7.3.2 日本の環境修復市場規模、民間別、2018年~202年
- 7.4 日本の環境修復市場規模:媒体別
- 7.4.1 日本の環境修復市場規模:土壌別、2018年〜202年
- 7.4.2 日本の環境修復市場規模:地下水別、2018年〜202年
- 8 日本の環境修復市場の機会評価
- 8.1 技術別、2024年〜202年
- 8.2 用途別、2024~202年
- 8.3 種類別、2024~202年
- 8.4 媒体別、2024~202年
- 9 競争環境
- 9.1 ポーターのファイブフォース
- 9.2 企業プロフィール
- 9.2.1 会社概要
- 9.2.1.1 スナップショット
- 9.2.1.2 会社概要
- 9.2.1.3 財務ハイライト
- 9.2.1.4 地理的洞察
- 9.2.1.5 事業セグメントと業績
- 9.2.1.6 製品ポートフォリオ
- 9.2.1.7 主要役員
- 9.2.1.8 戦略的な動きと開発
- 9.2.2 会社概要
- 9.2.3 会社名
- 9.2.4 会社名
- 9.2.5 会社名
- 9.2.6 会社名
- 9.2.7 会社名
- 9.2.8 会社名
- 10 戦略的提言
- 11 免責事項

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
