日本のマイクロフルイディクス市場規模(~2029年)

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
日本のマイクロ流体市場は、研究開発活動や健康、バイオテクノロジー、環境分野への応用に大きな重点を置いた、高い技術基盤を特徴としている。マイクロ流体工学は、化学的、生物学的、物理的プロセスを制御するための基本的な目標を達成するために、マイクロスケール内で少量の液体を操作する。診断学、薬物送達システム、分析手順に革命をもたらす可能性を秘めたこの理由から、マイクロ流体技術は日本で大きな関心と投資を集めている。ラボオンチップシステムやマイクロ流体センサーなど、最先端のマイクロ流体装置は現在日本で開発中である。これらは、高齢化に伴う医療の課題に対応するため、診断検査や分析アッセイの効率、感度、信頼性を向上させる。マイクロ流体工学は、日本における生物医学研究とヘルスケア・アプリケーションの中核をなしている。マイクロ流体工学は、迅速で正確な診断と薬剤スクリーニングを提供すると同時に、個別化された投薬アプローチの開発を推進する。マイクロ流体技術をゲノム解析やバイオマーカー検出と組み合わせることで、精密医療や新しい治療法の開発が可能になる。ヘルスケア以外にも、日本はマイクロ流体技術を環境モニタリング、食品安全検査、工業プロセス制御に応用している。マイクロ流体装置は、汚染物質、病原体、化学化合物をリアルタイムで分析し、環境の持続可能性と産業の効率性を実現する。東京大学や京都大学のような日本の確固たる学術研究機関が、マイクロ流体工学の技術革新を牽引している。学術界、産業界、政府間の相互作用は、マイクロ流体ソリューションの技術移転、製品開発、商業化を促進する。独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、日本市場向けの医療機器および診断機器の認可を管理する。製品の安全性と有効性を確保することを目的とした厳格な性質を持つ規制要件は、これらの要素を考慮して構築された参入戦略に影響を与え、商業化のスケジュールを推進する。
Bonafide Research社の調査レポート「日本のマイクロフルイディクス市場概要、2029年」によると、日本のマイクロフルイディクス市場は2024年から2029年にかけて年平均成長率16%以上で成長すると予測されている。日本のマイクロフルイディクス発展の軌跡は、技術の進歩、急速な都市化のような社会の動向、さらなる技術革新を支援する政府の制度を通じて活用されている。マイクロ流体技術における日本の発展は、精密医療と生物医学研究において日本を世界の最前線に押し上げる。最先端のラボオンチップ技術やマイクロ流体装置は、診断のスピードと精度を向上させることで、病気を時間内に特定し、同時に適切な治療法、さらには個々の患者の要求に合わせた薬物送達システムの準備にまで介入する余地を提供することで、診断に関して大きな役割を果たしている。これらの出来事が特別なのは、高齢化が進み、医療負担が増大し、医療提供の効率性と有効性の両方を実現する破壊的イノベーションを必要とする医療需要が高まっている日本という背景があるからだ。さらに、急速な都市化や大都市圏への人口集中といったトレンドが、都市部の医療現場で展開可能なポータブル診断装置やポイントオブケア検査技術といった高度な医療ソリューションを求めている。
研究開発から技術の商業化、市場拡大まで、日本のマイクロフルイディクスの展望における全体像を描き出すために、政府の制度やイニシアティブが一体となって機能している。科学技術基本計画で示された日本の再生戦略は、技術主導型産業の国際競争力を日本がリードする手段として、とりわけハイテク分野への投資に重点を置いてきた。これらの制度は、研究開発プロジェクトへの資金提供、技術移転に関する助成金、マイクロ流体工学の革新的応用に携わる新興企業や小規模企業への奨励金を提供している。
日本のマイクロ流体市場は、様々な製品とアプリケーションを持つ成長産業分野である。マイクロ流体ベースの装置は、主に診断、創薬、化学合成などにマイクロ流体を応用した一体型システムである。これらの装置には、少ないサンプル量、高いスループット、反応条件の厳密な制御など、数多くの利点がある。日本におけるマイクロ流体ベースの装置の例としては、ポイントオブケア診断装置、創薬プラットフォーム、化学合成システムなどがある。マイクロ流体コンポーネントは、マイクロ流体ベースの装置を構成する微小構造体である。開発されたマイクロ流体装置には、マイクロチャンネル、マイクロポンプ、マイクロバルブ、マイクロセンサー、マイクロアクチュエーターなどがある。マイクロチャンネルは、マイクロ流体装置内のユーティリティの移送に最も一般的に利用されているマイクロ流体部品である。マイクロポンプは流路の調節に利用され、次いでマイクロバルブは流路の制御に利用される。流体内の物理的・化学的特性の変化はマイクロセンサーによって検出され、マイクロアクチュエータは流体を操作する。ガラスベースのマイクロチャンネル、圧電マイクロポンプ、マイクロバルブは、日本におけるマイクロ流体工学を構成する要素の一部であり、主にバイオテクノロジーや医療装置で使用されている。
日本のマイクロ流体市場は、豊富な製造経験と広範な研究により、材料の使用という点で差別化されている。日本のマイクロ流体分野ではポリマーが優勢であり、単に汎用性と手頃な価格によって開かれた道をたどってきた。しかし、PDMS(ポリジメチルシロキサン)が依然として皆の憧れであるとすれば、代替ポリマーへの流れは現在進行中である。例えば、住友化学は最近、マイクロ流体用途をターゲットにした次世代高性能ポリマーを2023年にも発表した。このポリマーは、従来のPDMSに比べて耐薬品性に優れ、光学的透明性が向上しているため、高度な生物医学研究のあらゆる要件を満たすことができる。このポリマーベースのマイクロ流体チップは、がんの早期診断を強化する目的で、循環腫瘍細胞の検出に応用されている。ガラスは、日本のマイクロ流体工学、特に耐薬品性とともに高い光学的透明性が要求されるアプリケーションに不可欠であった。AGC社は、マイクロ流体装置にこの新しいクラスの極薄ガラスを製造した。このガラスは2024年初頭に市場に投入される予定で、高精度のマイクロ流体アプリケーションにおいて最も重要な特徴である驚異的な平坦性と表面品質を誇っている。日本のシリコンマイクロフルイディクスは、強力な半導体産業に基づいている。つい最近、日立ハイテクは、半導体での経験を基にした、単一細胞分析用のシリコンベースのマイクロ流体プラットフォームを発表した。これは、マイクロエレクトロニクスと流体チャンネルを対称的かつ一体的に組み合わせたシステムで、細胞の高精度な操作と分析を可能にする。このシステムは2023年半ばにシリアで発売され、すぐに日本の大手製薬会社が薬剤スクリーニングや個別化医療研究のために導入する。日本では、紙ベースのマイクロ流体工学は、特に低コストの診断において、かなりの役割を果たしている。現在、大阪大学の研究者たちは、食中毒病原体の迅速な同定が可能な紙ベースのマイクロ流体装置を開発した。日本の食品安全当局で実地試験されたこの環境に優しく費用対効果の高いソリューションは、日本の非常に厳しい食品安全基準を満たそうとしている。日本のマイクロ流体におけるセラミック材料のニッチアプリケーションは、高温や過酷な化学環境下で展開される主要な用途に直面している。京セラ株式会社は、化学合成用途のセラミック製マイクロ流体リアクターを開発している。このような製品は、ファインケミカル産業におけるプロセス強化の目的で2023年後半に発売され、先端材料と精密製造における日本のリードを証明することになるだろう。ハイドロゲル・ベースのマイクロ流体工学への関心は、組織工学への応用をターゲットとして、現在日本で急上昇している。理化学研究所生命システム動態研究センターの研究チームは、3次元組織モデルの作製を目指し、ハイドロゲル・ベースのマイクロ流体プラットフォームの開発を進めており、「wasse」と名付けられたこのシステムは、今年初めに東京で開催されたバイオエンジニアリング学会で発表された。このシステムは現在、薬物検査や再生医療に応用するための試験中である。
アプリケーション別に見ると、日本のマイクロ流体市場はあらゆる分野で力強く成長しており、これは日本のハイテク大国とイノベーション重視を反映している。日本の高齢化社会と予防医療重視が、この分野を動かしている。例えば、デンカ・カンパニー・リミテッドは2024年初頭に、インフルエンザとCOVID-19を同時に検出するマイクロ流体ベースの迅速検査法を開発したと発表した。この検査は、デンカ独自のマイクロ流体技術を採用することで、15分以内に結果が得られ、非常に効率的なポイント・オブ・ケア解決策となる。日本の研究者たちは、複雑なマイクロ流体ベースのドラッグデリバリーシステム構築への道を切り開いている。東京大学の研究チームは、2023年までに神経疾患の治療に革命をもたらす可能性のある、脳内薬物送達をターゲットとしたマイクロ流体装置をつい最近開発した。この装置は、音響波によってマイクロバブル内にかろうじて封入された活性化合物の放出を制御するもので、先進的な治療アプローチへの日本の貢献を証明している。日本の製薬業界は、創薬と薬剤開発にマイクロ流体工学を活用している。日本最大の製薬会社の一つである武田薬品工業株式会社は、研究開発プロセスにマイクロ流体臓器チッププラットフォームを採用した。このようなプラットフォームは、日本のバイオベンチャーと共同で開発されたもので、ヒト生体の機能を再現し、医薬品の有効性と毒性を評価する。マイクロ流体技術の開発は、日本の体外診断薬分野の一翼を担っている。シスメックス(株)は血液分析装置市場をリードしており、つい最近(2023年半ば)、マイクロ流体ベースの血液分析装置の新製品ラインを発表した。これは主に、採血量が非常に少ない小児や老人患者に有用である。マイクロ流体工学は、日本ではヘルスケア以外の多様なアプリケーションを感知しており、環境検査を研究している。島津製作所によると、水サンプル中のマイクロプラスチックを迅速に検出できるマイクロ流体装置が開発された。このシステムは、水のサンプルを数分以内に分析する前例のない能力をもたらし、日本の水環境におけるプラスチック汚染に対する高まる懸念に応えるものである。横河電機は、プロセス産業向けのマイクロ流体ベースのインライン化学分析装置を発表した。このシステムは、化学組成を考慮する際にリアルタイム制御を提供し、工業プロセスにおける生産効率と品質を向上させる。
日本のマイクロ流体市場の様々なエンドユーザーには、CROや産業用ユーザーを含む他の事業体の他に、病院や診断センター、製薬会社やバイオテクノロジー会社、学術研究機関が含まれる。迅速で正確な診断ツールは、世界的に感染性の高い疾患の診断に求められている。病院や診断センターは、迅速で正確な診断が必要なため、この技術の重要なエンドユーザーである。特徴 マイクロ流体装置は、サンプル量が少なく、エンドユーザー志向の製品である。ポイント・オブ・ケア診断は、まさにこの装置が採用される場所である。日本では、製薬会社やバイオテクノロジー企業がマイクロ流体装置を創薬や開発、品質管理などに応用している。実際、マイクロ流体装置には、ハイスループット・スクリーニング、非常に少ないサンプル量、厳格で正確な反応条件の制御能力など、研究用途での使用を可能にする非常に多くの利点がある。例えば、日本の東ソー株式会社は、創薬開発のためのマイクロ流体ベースのシステムを持っている。マイクロ流体装置は、日本の学術研究機関において、生物学研究、化学合成、材料科学に広く利用されている。日本の企業である京都大学は、マイクロ流体装置を用いて単一細胞やその挙動に関する研究を行っている。日本におけるマイクロ流体装置の他の最終ユーザーには、契約研究機関や産業界のユーザーが含まれる。前者は主に創薬や医薬品開発にマイクロ流体装置を使用し、後者はプロセスの最適化や品質管理にマイクロ流体装置を使用している。例えば、日本の産業用ユーザーとしては、食品・飲料分析アプリケーション用のマイクロ流体ベースのシステムを製造している島津製作所が挙げられる。
本レポートの考察
– 歴史的な年 2018
– 基準年 2023
– 推定年 2024
– 予測年 2029
本レポートでカバーされている側面
– マイクロ流体市場の展望とその価値、セグメント別の予測
– 様々な推進要因と課題
– 進行中のトレンドと開発
– 企業プロフィール
– 戦略的推奨
種類別
– マイクロ流体ベースの装置
– マイクロ流体コンポーネント(マイクロ流体チップ、マイクロポンプ、マイクロニードル、その他のマイクロ流体コンポーネントタイプ)
材料別
– ポリマー
– ガラス
– シリコン
– その他の材料(紙ベースのマイクロ流体、セラミックベースのマイクロ流体、ハイドロゲル、金属ベースのマイクロ流体)
用途別
– ポイントオブケア診断
– 薬物送達システム
– 医薬品・バイオテクノロジー研究
– 体外診断
– その他(環境検査、工業用途など)
エンドユーザー別
– 病院および診断センター
– 製薬・バイオテクノロジー企業
– 学術・研究機関
– その他(委託研究機関、産業用ユーザーなど)
レポートのアプローチ
本レポートは一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。はじめに、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために二次調査を行った。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源からなる。二次情報源からデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを行い、市場のディーラーや流通業者と取引コールを行うことによって実施した。その後、消費者を地域、階層、年齢層、性別で均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データが手に入れば、二次ソースから得た詳細の検証を始めることができる。
対象読者
本レポートは、マイクロ流体業界に関連する業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を調整するのに役立つ。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできる。
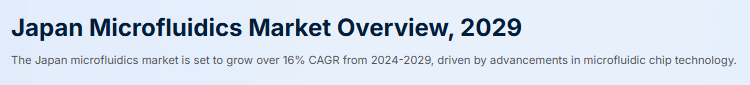
目次
- 1. 要旨
- 2. 市場構造
- 2.1. 市場考察
- 2.2. 前提条件
- 2.3. 制限事項
- 2.4. 略語
- 2.5. 情報源
- 2.6. 定義
- 2.7. 地理
- 3. 研究方法
- 3.1. 二次調査
- 3.2. 一次データ収集
- 3.3. 市場形成と検証
- 3.4. 報告書作成、品質チェック、納品
- 4. 日本のマクロ経済指標
- 5. 市場ダイナミクス
- 5.1. 市場促進要因と機会
- 5.2. 市場の阻害要因と課題
- 5.3. 市場動向
- 5.3.1. XXXX
- 5.3.2. XXXX
- 5.3.3. XXXX
- 5.3.4. XXXX
- 5.3.5. XXXX
- 5.4. コビッド19効果
- 5.5. サプライチェーン分析
- 5.6. 政策と規制の枠組み
- 5.7. 業界専門家の見解
- 6. 日本マイクロ流体市場の概要
- 6.1. 市場規模(金額ベース
- 6.2. 市場規模および予測、製品種類別
- 6.3. 市場規模・予測:素材別
- 6.4. 市場規模・予測:用途別
- 6.5. 市場規模・予測:エンドユーザー別
- 6.6. 市場規模・予測:地域別
- 7. 日本のマイクロフルイディクス市場のセグメンテーション
- 7.1. 日本マイクロ流体市場:種類別
- 7.1.1. 日本のマイクロ流体市場規模、マイクロ流体ベースの装置別、2018年〜2029年
- 7.1.2. 日本のマイクロ流体市場規模、マイクロ流体コンポーネント別、2018年~2029年
- 7.2. 日本のマイクロ流体市場規模、材料別
- 7.2.1. 日本のマイクロ流体市場規模、ポリマー別、2018年~2029年
- 7.2.2. 日本のマイクロ流体市場規模、ガラス別、2018-2029年
- 7.2.3. 日本のマイクロ流体市場規模、シリコン別、2018-2029年
- 7.2.4. 日本のマイクロ流体市場規模、その他別、2018-2029年
- 7.3. 日本マイクロ流体市場:用途別
- 7.3.1. 日本のマイクロ流体市場規模:ポイントオブケア診断薬別、2018年~2029年
- 7.3.2. 日本のマイクロ流体市場規模、薬物送達システム別、2018-2029年
- 7.3.3. 日本のマイクロ流体市場規模:製薬・バイオ研究別、2018年〜2029年
- 7.3.4. 日本のマイクロフルイディクス市場規模:体外診断薬別、2018年~2029年
- 7.3.5. 日本のマイクロ流体市場規模:その他別、2018年~2029年
- 7.4. 日本のマイクロ流体市場:エンドユーザー別
- 7.4.1. 日本のマイクロ流体市場規模:病院・診断センター別、2018年~2029年
- 7.4.2. 日本のマイクロ流体市場規模:製薬・バイオテクノロジー企業別、2018年~2029年
- 7.4.3. 日本のマイクロ流体市場規模:学術・研究機関別、2018年〜2029年
- 7.4.4. 日本のマイクロ流体市場規模:その他別、2018年~2029年
- 7.5. 日本のマイクロ流体市場:地域別
- 7.5.1. 日本のマイクロフルイディクス市場規模、北地域別、2018-2029年
- 7.5.2. 日本のマイクロ流体市場規模、東部別、2018-2029年
- 7.5.3. 日本のマイクロ流体市場規模、西日本別、2018-2029年
- 7.5.4. 日本のマイクロ流体市場規模、南別、2018-2029年
- 8. 日本マイクロ流体市場の機会評価
- 8.1. 製品種類別、2024年~2029年
- 8.2. 材料別、2024~2029年
- 8.3. 用途別、2024~2029年
- 8.4. エンドユーザー別、2024~2029年
- 8.5. 地域別、2024~2029年
- 9. 競争環境
- 9.1. ポーターの5つの力
- 9.2. 企業プロフィール
- 9.2.1. 会社1
- 9.2.1.1. 会社概要
- 9.2.1.2. 会社概要
- 9.2.1.3. 財務ハイライト
- 9.2.1.4. 地理的洞察
- 9.2.1.5. 事業セグメントと業績
- 9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
- 9.2.1.7. 主要役員
- 9.2.1.8. 戦略的な動きと展開
- 9.2.2. 企業2
- 9.2.3. 会社3
- 9.2.4. 4社目
- 9.2.5. 5社目
- 9.2.6. 6社
- 9.2.7. 7社
- 9.2.8. 8社
- 10. 戦略的提言
- 11. 免責事項
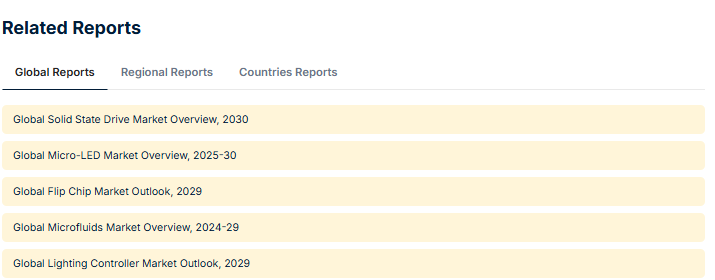
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
