日本の手すり市場規模(~2029年)

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
日本の鉄道輸送の歴史は、近代化、戦時体制への対応、経済変革、技術革新など、日本のダイナミックな歩みを反映しています。1872年、イギリスの専門技術を導入して建設された日本初の鉄道が開通し、東京と横浜が結ばれました。この時期、政府は日本鉄道のような私鉄を育成し、日本は経済と軍事の強化を目指し、鉄道網を拡大しました。しかし、日露戦争で物流が困難になったため、政府は1906年に鉄道を国有化し、日本政府鉄道(JGR)を設立。戦間期は鉄道技術の発展とネットワークの拡大が顕著でしたが、第二次世界大戦により軍事輸送が優先されるようになり、旅客サービスは縮小されました。戦後、鉄道システムは再建され、1949年に日本国有鉄道(JNR)として再ブランド化されました。しかし、1980年代までに国鉄は負債を抱え、1987年に日本鉄道(JR)グループとして知られる地域企業への歴史的な民営化に至りました。国鉄の負債を処理するために税金が投入されたこの再編は、日本の鉄道業界を活性化し、現在では時速600キロという前例のない速度で走行するよう設計された磁気浮上式新幹線のような革新的なベンチャー企業も含まれるようになりました。今日、民間と公共の利害関係者が協力して、効率性、安全性、そして象徴的な新幹線で有名な、27,700キロメートルに及ぶ広範な線路網を維持しています。このネットワークは主要都市を結ぶだけでなく、駅周辺の開発を促進し、豪華な列車体験を提供することで地域経済を支えています。将来の拡張は、遠隔地でのアクセシビリティの向上を目指し、卓越したエンジニアリングと文化的意義の世界的モデルとしての日本の鉄道を強化するものです。
Bonafide Research社の調査レポート「日本の手すり市場の展望、2029年」によると、日本の手すり市場は2024年から29年までに6億8000万米ドル以上に拡大すると予測されています。2023年現在、同市場は3,900万トンを超える貨物の輸送に成功しており、国家物流の枠組みにおける同市場の重要な役割を裏付けています。このような成長が見込まれる背景には、鉄道技術の進歩と、ロジスティクス・プロバイダーが優先順位を高めている持続可能な輸送ソリューションへの関心の高まりがあります。例えば、東急電鉄のような企業は、再生可能エネルギーのみで運営することを約束し、環境意識の高い消費者や企業にアピールしています。さらに、自動化やリアルタイムの追跡システムなど、ロジスティクスにおける技術革新は、鉄道貨物セクターにおける業務効率とサービス品質を大幅に向上させています。自動荷役システムの採用や安全対策の強化など、鉄道インフラの近代化に向けた投資も、鉄道貨物サービスの信頼性とスピードの向上につながると予想されます。日本が物流市場の進化する需要に対応し続けるなか、グリーン技術と革新的慣行の統合は、鉄道貨物部門を持続的成長 と競争力に向けて位置づけるうえできわめて重要である。
日本は、革新的な新幹線システムや、新たな磁気浮上式鉄道(磁気浮上式鉄道)などを通じて、鉄道技術のフロントランナーとしての地位を確立してきた。1964年から運行されている新幹線ネットワークは、特定の路線で最高時速320kmを達成する能力を持ち、鉄道輸送における現代の進歩を象徴しています。主な技術的特徴としては、1,435 mmの標準軌間、連続溶接レールの使用、バラスト軌道とスラブ軌道の組み合わせなどが挙げられます。さらに、自動列車制御(ATC)システムの導入により、従来の線路脇の信号機が不要になり、集中的な交通制御と列車位置のリアルタイム監視が可能になるため、密なスケジューリングが容易になり、遅延が最小限に抑えられるため、安全性が向上します。磁気浮上方式は、摩擦を大幅に低減し、最高時速505キロ(314マイル)を可能にするもので、試験走行では時速603キロ(375マイル)の世界記録を達成しています。東京と名古屋を結ぶ中央新幹線プロジェクトでは、磁気浮上式鉄道技術を活用し、両都市間の所要時間を約50%短縮する予定です。さらに、鉄道運行へのロボット工学の統合に対する日本のコミットメントは、西日本鉄道が架線保守に人型ロボットを導入するなどの取り組みに表れており、労働力不足に対処し、日本の鉄道業界を前進させ続ける革新的精神を示しています。
日本の鉄道貨物輸送市場は、サービスの種類、貨物の種類、用途、距離によって区分され、それぞれが物流・輸送ニーズの異なる側面に対応している。サービスの種類別には、鉄道と道路や海運などの他の輸送手段を組み合わせて効率を高める複合一貫輸送があり、コンテナ化の傾向により成長しています。また、液体輸送用のタンク貨車、一般貨物用の貨車、生鮮品用の冷蔵車など、種類別に特化したサービスもあり、さまざまな業種に対応しています。貨物の種類別では、コンテナ貨物が特に複合一貫輸送用途で市場をリードしており、非コンテナ貨物や液体バルク貨物(化学品や石油)は特定の需要に対応しています。鉄道貨物の主な用途には、大規模な輸送ソリューションを必要とする石油・ガスや鉱業部門が含まれますが、その他の産業も市場規模に貢献しています。短距離、中距離、長距離という距離ベースのセグメンテーションは、輸送範囲に基づくロジスティクスの最適化により、価格設定やサービスオプションのカスタマイズを可能にします。これらのセグメントを総合すると、鉄道貨物が日本の輸送インフラにおいて多様かつ戦略的な役割を果たし、産業間の需要拡大に適応していることがわかります。
本レポートの対象
– 地域 グローバル
– 歴史年: 2018
– 基準年 2023
– 推定年 2024
– 予測年 2029
本レポートの対象分野
– 手すりの世界市場:その価値とセグメント別予測
– 地域別・国別の手すり市場分析
– 用途別手すりの分布
– 様々な促進要因と課題
– 進行中のトレンドと開発
– 企業プロフィール
– 戦略的提言
素材別
– 金属(ステンレススチール、アルミニウム)
– ガラス
– 木材
– 複合材
用途別
– 内装
– エクステリア
デザイン別
– ガラスパネル
– バルスター
– その他
エンドユーザー別
– 商業
– 家庭用
– 工業用
流通チャネル別
– 直接
– 間接販売
レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されています。まず、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために二次調査を実施しました。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源で構成されています。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引コールを実施しました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始しました。一次データを入手した後は、二次ソースから得た詳細の検証を開始しました。
対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、農業関連団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。
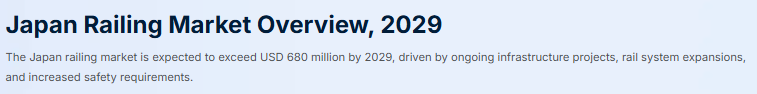
目次
1. 要旨
2. 市場構造
2.1. 市場考察
2.2. 前提条件
2.3. 制限事項
2.4. 略語
2.5. 情報源
2.6. 定義
2.7. 地理
3. 調査方法
3.1. 二次調査
3.2. 一次データ収集
3.3. 市場形成と検証
3.4. 報告書作成、品質チェック、納品
4. 日本のマクロ経済指標
5. 市場ダイナミクス
5.1. 市場促進要因と機会
5.2. 市場の阻害要因と課題
5.3. 市場動向
5.3.1. XXXX
5.3.2. XXXX
5.3.3. XXXX
5.3.4. XXXX
5.3.5. XXXX
5.4. コビッド19効果
5.5. サプライチェーン分析
5.6. 政策と規制の枠組み
5.7. 業界専門家の見解
6. 日本の手すり市場の概要
6.1. 市場規模(金額ベース
6.2. 市場規模および予測、素材別
6.3. 市場規模・予測:用途別
6.4. 市場規模・予測:デザイン別
6.5. 市場規模・予測:エンドユーザー別
6.6. 市場規模・予測:流通チャネル別
6.7. 市場規模・予測:地域別
7. 日本の手すり市場のセグメント
7.1. 日本の手すり市場、素材別
7.1.1. 日本の手すりの市場規模、金属別、2018年〜2029年
7.1.2. 日本の手すりの市場規模:ガラス別、2018年〜2029年
7.1.3. 日本の手すりの市場規模:木材別、2018年〜2029年
7.1.4. 日本の手すりの市場規模:複合材別、2018年〜2029年
7.2. 日本の手すり市場規模:用途別
7.2.1. 日本の手すりの市場規模:内装用途別、2018年〜2029年
7.2.2. 日本の手すりの市場規模:外装用途別、2018年~2029年
7.3. 日本の手すりの市場規模:デザイン別
7.3.1. 日本の手すりの市場規模、ガラスパネル別、2018年〜2029年
7.3.2. 日本の手すりの市場規模:バルスター別、2018年〜2029年
7.3.3. 日本の手すりの市場規模:その他別、2018年〜2029年
7.4. 日本の手すりの市場規模:エンドユーザー別
7.4.1. 日本の手すりの市場規模:商業施設別、2018年〜2029年
7.4.2. 日本の手すりの市場規模、家庭用別、2018年〜2029年
7.4.3. 日本の手すりの市場規模:産業用別、2018年~2029年
7.5. 日本の手すりの市場規模:流通経路別
7.5.1. 日本の手すりの市場規模:直接販売別、2018年〜2029年
7.5.2. 日本の手すりの市場規模:間接別、2018年~2029年
7.6. 日本の手すり市場:地域別
7.6.1. 日本の手すりの市場規模:北部別、2018年〜2029年
7.6.2. 日本の手すりの市場規模:東部別、2018年〜2029年
7.6.3. 日本の手すりの市場規模:西日本別、2018年~2029年
7.6.4. 日本の手すりの市場規模:南別、2018年~2029年
8. 日本の手すりの市場機会評価
8.1. 素材別、2024〜2029年
8.2. 用途別、2024~2029年
8.3. デザイン別、2024~2029年
8.4. エンドユーザー別、2024~2029年
8.5. 流通チャネル別、2024~2029年
8.6. 地域別、2024~2029年
9. 競合情勢
9.1. ポーターの5つの力
9.2. 企業プロフィール
9.2.1. 企業1
9.2.1.1. 会社概要
9.2.1.2. 会社概要
9.2.1.3. 財務ハイライト
9.2.1.4. 地理的洞察
9.2.1.5. 事業セグメントと業績
9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
9.2.1.7. 主要役員
9.2.1.8. 戦略的な動きと展開
9.2.2. 企業2
9.2.3. 企業3
9.2.4. 4社目
9.2.5. 5社目
9.2.6. 6社
9.2.7. 7社
9.2.8. 8社
10. 戦略的提言
11. 免責事項

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
