日本の繊維リサイクル市場規模(~2029年)

| 本報告書は、日本における繊維リサイクル市場についての詳細な分析を提供しており、市場の構造やダイナミクス、競争環境など多岐にわたる情報を含んでいます。 まず、要旨では、繊維リサイクル市場の現状と将来の見通しについて簡潔に述べられています。市場構造については、市場考察、前提条件、制限事項、略語、情報源、定義、地理的な要素が整理されており、これに基づいて市場の全体像が浮かび上がります。 調査方法に関しては、二次調査と一次データ収集の手法が示されており、市場形成と検証のプロセスが明記されています。報告書作成における品質チェックや納品についても触れられています。 日本のマクロ経済指標に基づく市場ダイナミクスでは、市場促進要因や機会、阻害要因や課題、そして最近の市場動向について詳述されています。また、コビッド19の影響やサプライチェーン分析、政策と規制の枠組み、業界専門家の見解も考察されています。 次に、日本の繊維リサイクル市場の概要が示され、市場規模や予測が金額ベースで整理されています。素材別、供給源別、繊維廃棄物別、プロセス別、地域別に詳細なデータが提供されています。 市場セグメントの分析においては、素材別や供給源別、繊維廃棄物別、プロセス別、地域別にわかりやすく分類されております。特に、各セグメントにおける市場規模の推移が2018年から2029年までの予測として示されています。 市場機会の評価についても、素材別、供給源別、繊維廃棄物別、プロセス別、地域別に分析が行われており、今後の成長が期待される領域が明示されています。 競争環境では、ポーターの5つの力を用いた分析が行われ、主要企業のプロフィールが詳細に紹介されています。各企業の会社概要や財務ハイライト、地理的洞察、事業セグメント、製品ポートフォリオ、戦略的な動きが整理されています。 最後に、戦略的提言が行われており、企業が今後の市場で成功するための方向性が示されています。報告書には免責事項も含まれており、データの使用における注意点が明記されています。このように、本報告書は日本の繊維リサイクル市場について、包括的かつ詳細な情報を提供しており、関係者にとって有益な資料となっています。 |
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
日本の繊維リサイクル市場は、主に環境保護と持続可能性という文化的倫理観によって支えられています。日本の消費者は、リサイクル繊維製品への需要を高めており、環境責任に関する美辞麗句に見合った購買を行おうとしています。政府は、繊維製品を含むあらゆる生活分野での持続可能性の推進に積極的です。政策や規制は、企業がリサイクルに取り組み、廃棄物を削減することを奨励しています。したがって、このような規制環境は、企業や消費者が持続可能な慣行に積極的に取り組むよう求められる支援的な枠組みを設定することによって、繊維製品リサイクル市場の繁栄を助長する環境を与えてきました。さらに、日本は技術的に非常に進んでおり、最先端の繊維リサイクル技術の開発において最前線に立ってきました。ケミカルリサイクルや、繊維リサイクルプロセスの効率を高める最先端の選別技術など、これらの技術革新はその最前線にあります。このような技術革新は、市場の成長に弾みをつけるだけでなく、日本が持続可能な繊維の分野で世界のリーダー的地位を占める道を開くことにも貢献しています。また、繊維産業、テクノロジー企業、研究機関の間に存在する実に緊密な協力関係は、成長の見通しをさらに高めます。この協力関係は、効果的なリサイクル方法を生み出し、持続可能な技術を社会に広く普及させ、高品質のリサイクル繊維製品を奨励することを目的としています。このようなセクター間の相乗効果は、繊維リサイクルへの全体的なアプローチにつながります。繊維廃棄物が環境に与える影響に対する日本の消費者の意識も、この市場成長の大きな原動力です。繊維リサイクルの利点に関する教育キャンペーンや広報活動を通じて、現在では消費者の行動が好転しています。このような意識の高まりにより、より多くの人々がリサイクルプログラムに参加し、リサイクル素材から製造された製品を積極的に選ぶようになっています。
Bonafide Research発行の調査レポート「日本の繊維リサイクル市場の概要、2029年」によると、日本の繊維リサイクル市場は2024年から2029年にかけて年平均成長率5%以上で成長すると予測されています。日本では、持続可能性が文化的価値観の一部となっており、消費者の行動やビジネスの進め方に大きな影響を与えています。これは、資源を大切にし、無駄を省き、コストを削減するという「もったいない」の概念に通じる世界観です。このような文化的世界観から、環境を尊重する習慣を取り入れることへの関心が高まり、人々や企業はリサイクルやアップサイクルの取り組みを加速させています。日本の消費者はリサイクル素材から作られた製品を受け入れやすい傾向にあり、環境に優しく、社会的責任の証であると考えることが多い。このような文化的基盤は、持続可能性が最優先され、革新的なリサイクル・ソリューションが最も歓迎される市場環境を提供する上で重要です。回収繊維をリサイクル繊維に変える可能性を最大化するためには、製品デザインと開発の面での革新が不可欠です。日本企業は、衣料品から家庭用品、工業用繊維製品に至るまで、リサイクル素材の新たな用途にますます手を広げています。こうした持続可能なファッションに敏感な顧客のために、リサイクル繊維を使用した衣料品シリーズをすでに作り始めているブランドもあります。現在進行中の技術革新のひとつは、長寿命でリサイクル可能な製品を提供する「循環型デザイン」です。日本における繊維リサイクルプロセスの効率性と有効性の向上における技術革新の役割は重要です。より優れた選別・処理技術により、消費者使用後の繊維製品からの有価繊維の回収率は大幅に向上しました。例えば、機械選別システムは人工知能と機械学習を用いて繊維の組成、色、品質によって繊維を選別し、より効率的なリサイクルを可能にしています。
日本の繊維リサイクル市場では、綿のカテゴリーがトップに君臨しています。これにはいくつかの要因があります。それは、綿が日本の繊維セクターで主に使用される素材のひとつであるため、廃棄物の量が多いこと。第二に、その生分解性という特性も、日本の環境意識の高さを考えれば、リサイクルに適しています。回収場所やリサイクル施設など、綿花リサイクルのためのインフラがすでに存在していることも、いくらか推進要因となっています。日本における繊維リサイクルの中で最も急成長している市場分野は、ポリエステルおよびポリエステル繊維。これは、ポリエステルが手頃な価格で耐久性に優れているため、繊維産業でポリエステルの利用が拡大していることが背景にあります。高度なポリエステル・リサイクル技術により、リサイクル・ポリエステルの生産がより現実的かつ低コストで可能になったことも、同分野の市場を牽引する要因となっています。もうひとつの原動力は、ポリエステルを含むプラスチック廃棄物の削減に日本が取り組んでいることでしょう。ナイロン・ナイロン繊維も、アパレルやその他の繊維製品、カーペットやフローリングなどの製品に再生ナイロンを使用して成長すると予測される分野です。ナイロンのリサイクルは綿やポリエステルほど盛んではありませんが、新しい高度な技術によってリサイクルが可能になりました。ウールのカテゴリーには、ウール繊維のリサイクルが含まれます。ウールは天然で生分解性がありますが、特に繊維の構造が異なるため、リサイクルは依然として困難です。しかし、日本ではいくつかのプロジェクトでウールのリサイクルが奨励されています。その他の分野には、シルク、レーヨン、混紡生地など、その他の繊維素材のリサイクルが含まれます。
日本の繊維リサイクル市場をリードしているのはアパレル廃棄物分野。これは主に、日本における衣料品の消費と廃棄の割合が高いことに起因しています。ファストファッションの流行、スタイルの変化、季節の衣服の文化的重要性といった要因が、大量の衣料廃棄物を生み出しているのです。また、日本の中古衣料品には、古くから発達してきた回収・リサイクル施設のネットワークが非常に広く、この分野の牙城を支えています。日本の繊維リサイクル市場では、家庭用家具廃棄物分野が成長しています。この成長は、寝具、カーテン、椅子張りなどの家庭用繊維製品をリサイクルすることの意義に対する消費者の認識と関心の高まりによるものである。日本が循環型経済を目指しているため、廃棄するよりもリサイクルすることがますます求められています。また、リサイクル技術の継続的な進歩により、家庭用繊維製品の処理とリサイクルがますます可能になり、この分野の成長を後押ししていることも大きな要因となっています。自動車廃棄物セグメントは、シートカバー、カーペット、エアバッグなど、自動車に使用されている繊維材料のリサイクルを指します。廃棄物の量はアパレル廃棄物ほど多くはありませんが、日本では使用済み自動車の数が増加しているため、この分野でのリサイクルが増加する機会があります。また、規制やイニシアチブが自動車のリサイクルを奨励しており、この分野の成長に拍車をかけています。その他には、産業用繊維製品、フィルター、その他雑多な繊維製品など、その他すべての排出源から出る繊維廃棄物が含まれます。これらの素材は繊維リサイクル市場の大きな割合を形成しているわけではありませんが、日本の廃棄物削減計画においては依然として重要です。
日本の繊維製品リサイクル市場は、消費者廃棄物後のカテゴリーが大半を占めており、消費者廃棄物後のカテゴリーは今期中に成長すると予想されています。これには、使用済みの衣類、寝具、その他の繊維製品など、耐用年数を終えて消費者によって廃棄された製品が含まれます。日本では消費率が高く、製品の耐久性が低いため、繊維廃棄物の発生割合が最も高く、市場を支配することになるでしょう。この分野の成長を後押ししているのは、繊維廃棄物による環境への影響とリサイクルの必要性に対する日本の消費者の意識の高まりです。日本では、古着屋、引き取りプログラム、自治体のリサイクル活動など、回収システムが発達しているため、消費者廃棄物後の繊維廃棄物がリサイクルされる経路が容易に確保されています。日本の繊維リサイクル市場において、消費者以前の廃棄物セグメントは小さい。プレコンシューマー廃棄物とは、加工段階で発生する廃棄物のことで、生地の切れ端、糸くず、端切れなどが含まれます。その理由は、日本の繊維メーカーが、素材を効率的に使用する生産方法を導入することで、廃棄物の発生を抑制しているためです。とはいえ、プレコンシューマー廃棄物のリサイクルは、埋立廃棄物の最小化と、より循環型の経済の達成に大きく関係している。
現在、日本の繊維リサイクル市場を支配しているのは、メカニカル・リサイクル分野です。メカニカル・リサイクルとは、繊維廃棄物を物理的に繊維や細片などの小さな構成要素に分解し、再利用またはリサイクルするプロセスである。このプロセスは、シンプルでコストが低く、多くの繊維素材、特に綿やその他の天然繊維に適用できるため、日本で広く利用されてきました。また、回収場所や処理施設など、メカニカル・リサイクルのためのインフラがすでに整備されていることも後押ししている。ケミカルリサイクル分野は、日本の繊維リサイクル市場の中で最も急速に成長している分野です。ケミカルリサイクルとは、繊維廃棄物を化学的手段によって分子要素にまで分解し、新しい素材に再構成するプロセスを指します。そのため、機械的なリサイクルが難しいポリエステルやナイロンなどの合成繊維のリサイクルに期待されています。解重合や溶剤を使用したプロセスなどのリサイクル技術の向上は、ケミカルリサイクルの効率向上とコスト削減を推進するものです。さらに、プラスチック廃棄物の削減と循環型経済の確立に向けた日本の決意が、ケミカルリサイクル技術への投資と研究の増加を促しています。
本レポートの考察
– 歴史的な年 2018
– 基準年 2023
– 推定年 2024
– 予測年 2029
本レポートの対象分野
– 繊維リサイクル市場の展望とその価値とセグメント別予測
– 様々な促進要因と課題
– 進行中のトレンドと開発
– 企業プロフィール
– 戦略的提言
素材別
– 綿
– ポリエステル&ポリエステル繊維
– ナイロン・ナイロン繊維
– ウール
– その他
発生源別
– アパレル廃棄物
– 住宅設備廃棄物
– 自動車廃棄物
– その他
エンドユーザー別
– アパレル
– 家庭用家具
– 産業・施設
– その他
繊維廃棄物別
– ポストコンシューマー
– プレコンシューマー
工程別
– 機械
– 化学
レポートのアプローチ
本レポートは一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されています。まず二次調査は、市場を理解し、そこに存在する企業をリストアップするために使用されます。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースなどの第三者情報源で構成されています。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要プレーヤーに電話インタビューを実施し、市場のディーラーやディストリビューターとの取引コールを実施することによって行われました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始しました。一次データが得られれば、二次ソースから得た詳細の検証を開始することができます。
対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、団体、繊維リサイクル業界関連組織、政府機関、その他ステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。

目次
- 1. 要旨
- 2. 市場構造
- 2.1. 市場考察
- 2.2. 前提条件
- 2.3. 制限事項
- 2.4. 略語
- 2.5. 情報源
- 2.6. 定義
- 2.7. 地理
- 3. 調査方法
- 3.1. 二次調査
- 3.2. 一次データ収集
- 3.3. 市場形成と検証
- 3.4. 報告書作成、品質チェック、納品
- 4. 日本のマクロ経済指標
- 5. 市場ダイナミクス
- 5.1. 市場促進要因と機会
- 5.2. 市場の阻害要因と課題
- 5.3. 市場動向
- 5.3.1. XXXX
- 5.3.2. XXXX
- 5.3.3. XXXX
- 5.3.4. XXXX
- 5.3.5. XXXX
- 5.4. コビッド19効果
- 5.5. サプライチェーン分析
- 5.6. 政策と規制の枠組み
- 5.7. 業界専門家の見解
- 6. 日本の繊維リサイクル市場の概要
- 6.1. 市場規模(金額ベース
- 6.2. 市場規模および予測、素材別
- 6.3. 市場規模および予測:供給源別
- 6.4. 市場規模および予測:繊維廃棄物別
- 6.5. 市場規模および予測:プロセス別
- 6.6. 市場規模および予測:地域別
- 7. 日本の繊維リサイクル市場のセグメント
- 7.1. 日本の繊維リサイクル市場、素材別
- 7.1.1. 日本の繊維リサイクル市場規模、綿別、2018年〜2029年
- 7.1.2. 日本の繊維リサイクル市場規模:ポリエステル・ポリエステル繊維別、2018年〜2029年
- 7.1.3. 日本の繊維リサイクル市場規模:ナイロン・ナイロン繊維別、2018年〜2029年
- 7.1.4. 日本の繊維リサイクル市場規模:ウール別、2018年〜2029年
- 7.1.5. 日本の繊維リサイクル市場規模:その他別、2018-2029年
- 7.2. 日本の繊維製品リサイクル市場:供給源別
- 7.2.1. 日本の繊維リサイクル市場規模:アパレル廃棄物別、2018年〜2029年
- 7.2.2. 日本の繊維リサイクル市場規模:家庭用家具廃棄物別、2018年~2029年
- 7.2.3. 日本の繊維リサイクル市場規模:自動車廃棄物別、2018年〜2029年
- 7.2.4. 日本の繊維製品リサイクル市場規模:その他別、2018年~2029年
- 7.3. 日本の繊維リサイクル市場:繊維廃棄物別
- 7.3.1. 日本の繊維製品リサイクル市場規模:廃棄物別、2018年〜2029年
- 7.3.2. 日本の繊維製品リサイクル市場規模、プレコンシューマー別、2018年〜2029年
- 7.4. 日本の繊維製品リサイクル市場:プロセス別
- 7.4.1. 日本の繊維製品リサイクル市場規模、機械別、2018年〜2029年
- 7.4.2. 日本の繊維リサイクル市場規模、化学別、2018年〜2029年
- 7.5. 日本の繊維製品リサイクル市場規模:地域別
- 7.5.1. 日本の繊維リサイクル市場規模:北地域別、2018年〜2029年
- 7.5.2. 日本の繊維製品リサイクル市場規模:東部別、2018年〜2029年
- 7.5.3. 日本の繊維リサイクル市場規模:西日本別、2018年~2029年
- 7.5.4. 日本の繊維リサイクル市場規模:南別、2018年~2029年
- 8. 日本の繊維リサイクル市場の機会評価
- 8.1. 素材別、2024〜2029年
- 8.2. 供給源別、2024~2029年
- 8.3. 繊維廃棄物別、2024~2029年
- 8.4. プロセス別、2024~2029年
- 8.5. 地域別、2024~2029年
- 9. 競争環境
- 9.1. ポーターの5つの力
- 9.2. 企業プロフィール
- 9.2.1. 企業1
- 9.2.1.1. 会社概要
- 9.2.1.2. 会社概要
- 9.2.1.3. 財務ハイライト
- 9.2.1.4. 地理的洞察
- 9.2.1.5. 事業セグメントと業績
- 9.2.1.6. 製品ポートフォリオ
- 9.2.1.7. 主要役員
- 9.2.1.8. 戦略的な動きと展開
- 9.2.2. 企業2
- 9.2.3. 企業3
- 9.2.4. 4社目
- 9.2.5. 5社目
- 9.2.6. 6社
- 9.2.7. 7社
- 9.2.8. 8社
- 10. 戦略的提言
- 11. 免責事項
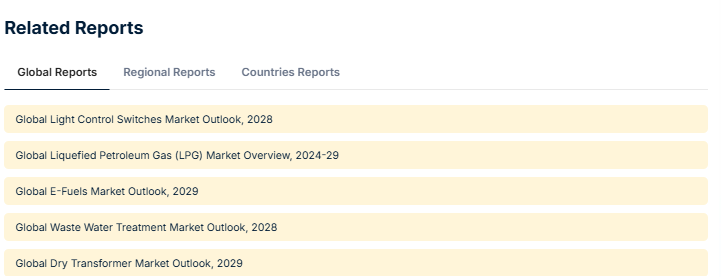
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
